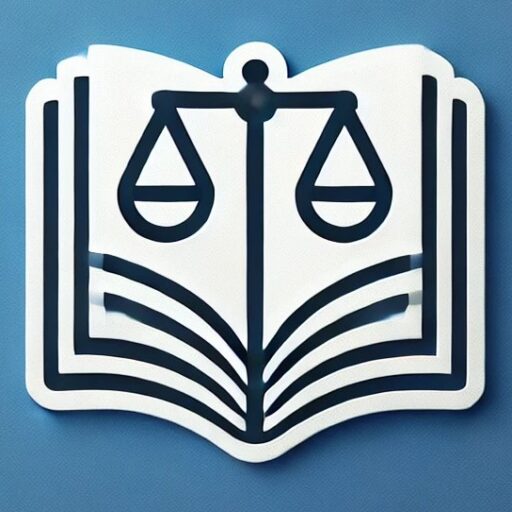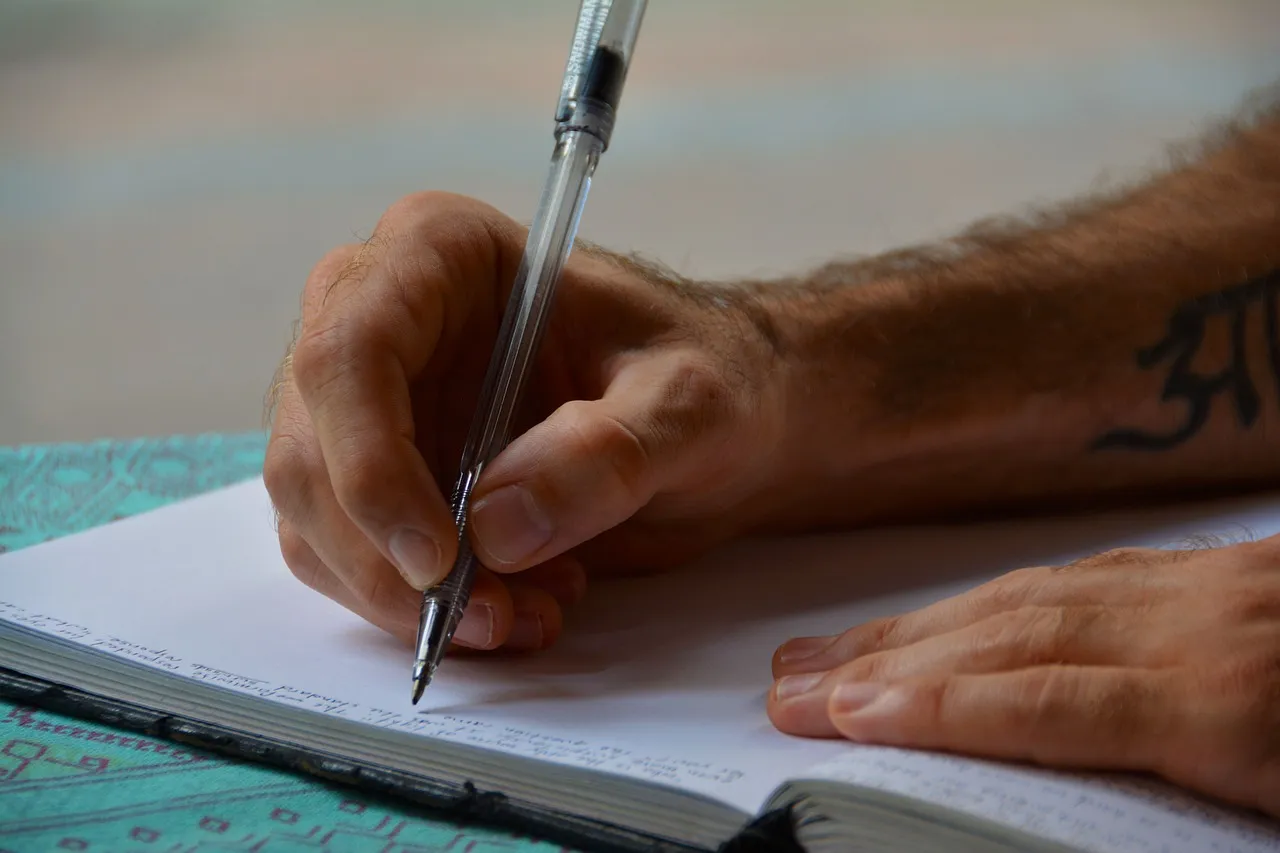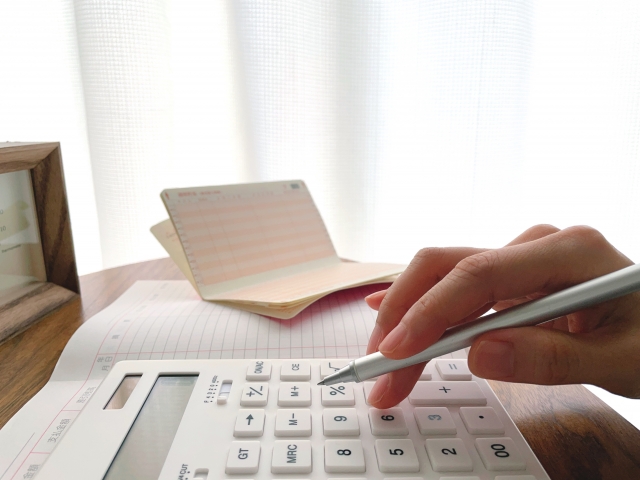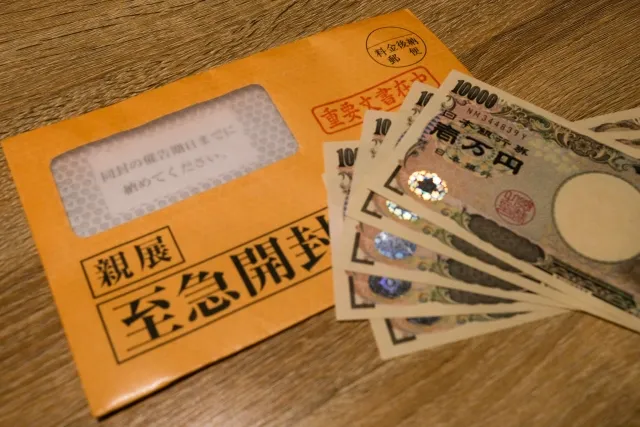自己破産したら入院給付金は没収される?手元に残す方法と公的支援
投稿日: 2025.08.05 | 更新日: 2025.08.05

借金の返済が難しく、自己破産を考えている方の中には、
「もし入院中に保険から給付金を受け取ったら、それも没収されるの?」と心配になる方もいるでしょう。
たとえば、ケガや病気で入院した際に、医療保険から入院給付金を受け取るケースです。
このような給付金は、自己破産の際に「財産」とみなされる可能性もありますが、すべてが没収対象になるわけではありません。
給付金の使い道や受け取ったタイミング、保険の契約内容などによって判断が分かれるため、対応は非常に複雑です。
医療費の支払いにあてる必要がある場合など、生活に欠かせない資金として扱われることもあるため、一律に処分されるとは限りません。
少しでも不安がある場合は、自己破産に詳しい弁護士に相談して判断を仰ぐことが大切です。
ケースによって対応が変わるため、早めに専門家に確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
この記事では、入院給付金を手元に残す方法や、入院給付金と自己破産の関係について詳しく解説していきます。
入院給付金は自己破産で没収される?
借金のことで悩んでいる中で、さらに入院まで重なってしまうと、とても不安になりますよね。
しかし、結論から言えば、自己破産をしても入院給付金は手元に残せる可能性が高いと考えて問題ありません。
とはいえ、自己破産の制度には細かいルールがあり、事情によっては判断が分かれる場合もあるため、給付金の種類や受け取り方によっては、財産とみなされることもあるので注意しましょう。
まずは、なぜ自己破産で財産が没収されるのかを確認しておきましょう。
▼関連記事
自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説
自己破産では20万円以上の価値がある財産は没収される
自己破産は、返済不能となった人の借金を法的に免責にする制度です。
借金が免責されることで、債務者は生活を立て直すことが可能になりますが、その一方で、貸した側(債権者)は大きな損失を被ることになります。
そのため、破産者が保有する財産のうち、一定以上の価値があるものについては裁判所が処分し、その売却代金を債権者に分配するという仕組みになっています。
このように、自己破産は債務者を救済する制度であると同時に、債権者の立場にも一定の配慮がなされている制度です。
具体的には、1点あたり20万円以上の価値がある財産が没収の対象となります。
・家やマンション・土地などの不動産
・自動車やバイク
・貴金属・時計・ブランド品など
・株式などの有価証券
・生命保険の解約返戻金
逆に、99万円以下の現金や、生活に必要な家具・家電などの最低限の財産は、原則として手元に残せます。
つまり、自己破産をしても生活そのものが立ち行かなくなるようなことはありません。
自己破産手続きが開始した時点で保険契約がある場合は没収対象になる
入院後に受け取れる入院給付金についても、実は金額によっては没収の対象となる可能性があります。
具体的には、入院給付金が20万円を超える場合、その超過分が自己破産の手続きにおいて処分されることがあるのです。
入院給付金を受け取れる生命保険に加入している場合、その保険契約は「将来受け取れる財産」と見なされます。
そのため、実際に給付金を請求しているかどうかに関係なく、破産手続きの時点で契約が存在していれば、入院給付金は破産財団に含まれる対象となります。
第三十四条
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】
破産財団とは、自己破産において処分の対象となる財産のことを指します。
過去の判例でも、「まだ受け取っていない入院給付金であっても、破産財団に含まれる」という判断が下された例があります。
自由財産の拡張で手元に残せる可能性がある
「手元に残せると思っていたのに、没収されてしまうのか」と不安になるかもしれません。
しかし、ここで重要なのが「自由財産の拡張」という制度です。
自己破産では、原則として20万円以上の財産が破産財団として没収の対象になりますが、
生活の維持に必要な財産については、例外的に手元に残せるケースがあります。
これが「自由財産の拡張」と呼ばれる仕組みです。
たとえば、入院給付金が生活費としてどうしても必要であると認められた場合、
破産管財人が裁判所に申立てを行うことで、一定の範囲内で給付金を手元に残すことが可能になります。
自由財産の拡張は、原則として現金などを含めて総額99万円までであれば認められる傾向にあります。
この枠内であれば、たとえ給付金が一度「破産財団」に含まれても、最終的に没収されずに済む可能性が高いということです。
第三十四条
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】
実際の運用は裁判所によって異なる
ただし、これはあくまで東京地方裁判所で自己破産を申し立てた場合の一例にすぎません。
実際には、自由財産の拡張をどこまで認めるかは、裁判所によって運用に差があるのが現実です。
そのため、「入院給付金を確実に受け取れる」とは一概に言えません。
自己破産を検討している場合は、依頼する弁護士とよく相談し、状況に応じた対応を確認することが大切です。
自己破産後に入院給付金を手元に残すためには
自己破産における入院給付金の扱いについて、ここまでで大まかな仕組みは理解できたかと思います。
ここからは、自己破産後に入院給付金を手元に残すために注意すべきポイントについて解説します。
担当の弁護士にしっかりと相談する
最も重要なのは、自己破産を依頼した弁護士としっかり相談することです。
たとえば、破産後も高額な医療費の支払いが継続するような事情がある場合には、入院給付金が生活に必要不可欠な資金と判断され、手元に残せる可能性も十分にあります。
ただし、法律上は自己破産を申し立てた時点で契約していた保険に基づく給付金は、一度「破産財団」に組み込まれる=没収の対象となるのが原則です。
入院給付金を最終的に受け取るためには、その給付金がなければ破産後の生活を再建できないという事情を、裁判所に説明・証明する必要があります。
そのためにも、自己破産に詳しい弁護士と十分に打ち合わせを行い、自分の生活状況や医療費の見通しなどを共有しておくことが大切です。
破産の手続きでは給付金について正直に申告する
「入院給付金はまだ受け取っていないし、自己破産が終わってから申請すればバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、それは絶対にしてはいけない行為です。
自己破産の手続きでは、裁判所が選任する破産管財人(はさんかんざいにん)が、破産者の財産状況を徹底的に調査します。
この調査には、生命保険や医療保険の契約内容も含まれており、給付金の有無も必ず確認されます。
つまり、たとえ給付金をまだ受け取っていなかったとしても、保険契約が存在する限り、給付金の存在を隠し通すことはできません。
さらに、自己破産の手続きにおいて財産を意図的に隠すことは重大な違反行為とされます。
もし入院給付金の存在を隠していたことが発覚した場合、最悪の場合、自己破産の免責が認められない=借金の帳消しが無効になる恐れもあります。
正直に、すべての財産情報を申告することが、自己破産を成功させるための第一歩です。
不安がある場合には、必ず弁護士に相談し、正しい手続きを進めるようにしましょう。
自由財産の拡張を主張する
これまでの内容を踏まえると、自己破産において入院給付金を手元に残すためには、まず弁護士に正直に相談し、適切に申告することが重要であると言えます。
そのうえで、「自由財産の拡張」の申立てを行えば、入院給付金を受け取れる可能性は十分にあります。
自由財産の拡張は、原則として現金を含めた総額99万円以内であれば、裁判所に認められるケースが多いとされています。
たとえば、現金や預金が50万円あり、さらに入院給付金として50万円を受け取る予定である場合、
99万円の枠を1万円だけ超えることになります。この場合、その超過分1万円だけが没収の対象になるといったイメージです。
入院給付金は例外的に99万円を超える拡張が認められる可能性もある
とはいえ、「99万円」という金額に不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、自己破産によってほかの借金がすべて免除されることを考えれば、十分に大きな救済となります。
また、重い病気などで継続的に高額な医療費が必要になったり、就労が困難な状態が続くような特殊な事情がある場合には、99万円を超える範囲での自由財産の拡張が認められることもあります。
いずれにしても、個別の事情によって判断は変わるため、担当の弁護士と十分に相談しながら対応を進めることが何より大切です。
医療費の負担が不安な時は公的支援を利用しよう
借金に苦しんでいるなかで入院を経験すると、今後の医療費の負担についても不安を感じるのは当然のことです。
しかし、安心してください。日本には、そうした状況を支えるための公的な社会保障制度がいくつも用意されています。
これから紹介する制度は、すべて国や自治体が提供している公的な支援制度です。
そのため、自己破産をしている場合でも問題なく利用することができます。
医療費や生活費の不安を軽減する手段として、ぜひ参考にしてください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月あたりの医療費が高額になった場合に、一定の自己負担限度額を超えた分が後日払い戻される公的制度です。
この制度は、全国健康保険協会(協会けんぽ)などの健康保険組合が運営しています。
ただし、制度を利用するにあたって注意すべき点があります。
それは、まず医療費を全額支払う必要があるということです。
払い戻しを受けるまでには、審査や手続きの関係でおおむね3か月以上かかるとされています。
そのため、医療費の支払いが厳しい場合には、次に紹介する「高額医療費貸付制度」とあわせて利用するか、一時的に親族などから借りるなどの対応が現実的な方法となるでしょう。
高額医療費貸付制度
先ほど紹介した高額療養費制度は、医療費の一部があとから払い戻される制度ですが、
払い戻しまでに3か月以上かかることがあるため、すぐに医療費を用意できない場合には不安が残ります。
そのようなときに活用できるのが、高額医療費貸付制度です。
この制度では、高額療養費制度で支給される見込み額の約8割を無利子で借りることができるため、
当面の医療費の支払いが難しい場合でも安心です。
【参考:医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)- 全国健康保険協会】
限度額適用認定証
医療費が高額になることがあらかじめ分かっている場合には、「限度額適用認定証」を事前に取得しておくことをおすすめします。
この認定証を病院の窓口で提示することで、1か月あたりの医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
つまり、最初から大きな金額を支払う必要がなくなるため、経済的な負担を大きく減らすことができます。
なお、自己負担限度額は年齢や収入によって異なるため、詳しくは全国健康保険協会のホームページなどで確認してください。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えた場合に利用できる公的な支援制度です。
健康保険に加入している人であれば、基本的に誰でも申請可能で、会社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象となります。
一定の条件を満たせば、最長1年6か月間、給与のおおよそ3分の2程度が支給されるため、療養中の生活を支える助けになります。
傷病手当金の支給要件
・健康保険の被保険者である
・業務外のケガや病気によって仕事ができなくなった
・連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだ
・休業中に給与の支払いを受けていない
【参考:傷病手当金|全国健康保険協会 協会けんぽ】
生活保護制度
病気やケガが原因で働けない状態が長引き、収入もなくなってしまった場合には、生活保護制度の利用も検討する必要があります。
生活保護を受けられれば、医療費の自己負担が基本的になくなり、生活費の支援も受けられます。
「生活保護」と聞くと、ためらいを感じる方もいるかもしれませんが、
この制度は、生活が困難になった人が利用できる国の正当な支援制度です。
申請には一定の条件がありますが、働けない状況にある場合には、躊躇せず利用を検討するべき選択肢のひとつです。
【参考:生活保護制度|厚生労働省】
まとめ
自己破産を申し立てた時点で契約している保険については、その後に受け取れる入院給付金も没収の対象になる可能性があります。
ただし、「自由財産の拡張」という手続きによって、入院給付金を手元に残せる可能性もあるため、
制度のしくみを正しく理解したうえで、担当の弁護士としっかり相談することが大切です。
ここまでの説明で、自己破産と入院給付金の関係についての理解が深まったかと思います。
ただし、具体的な対応は一人ひとりの状況によって異なるため、何よりもまず、弁護士に相談することが解決への第一歩です。
借金問題は、自然に解決するものではありません。
早めに動き出すことで、ダメージを最小限に抑えられる可能性が高くなります。
なお、借金に関する相談は多くの弁護士事務所で無料で受け付けているので、不安を抱えている方は、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
関連記事

自己破産の陳述書には何を書けばいい?思い出せない時の対処法も紹介
2025.05/28

自己破産すると親にバレる?バレる理由や親への影響・対処法を解説
2025.05/27

自己破産前の名義変更は危険!車や家を残すための対処法
2025.05/25
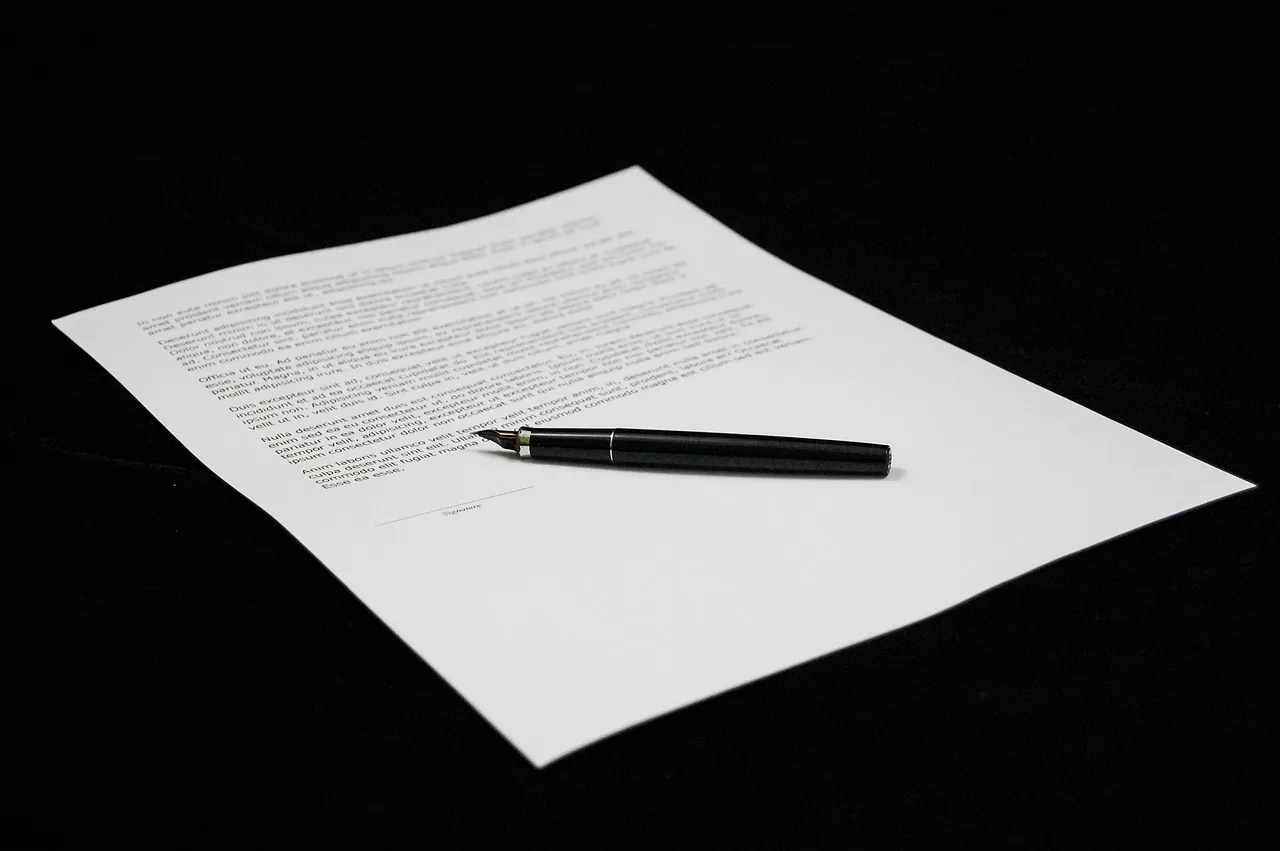
自己破産の書類が揃わないとどうなる?必要書類や対処法を解説
2025.05/25

自己破産でネット銀行の口座・財産隠しはバレる!リスクと対処法を解説
2025.05/19

奨学金を外して自己破産できる?対処法や保証人への影響を解説
2025.05/19