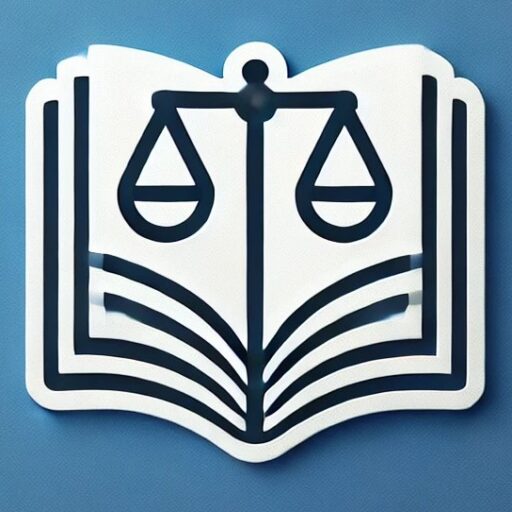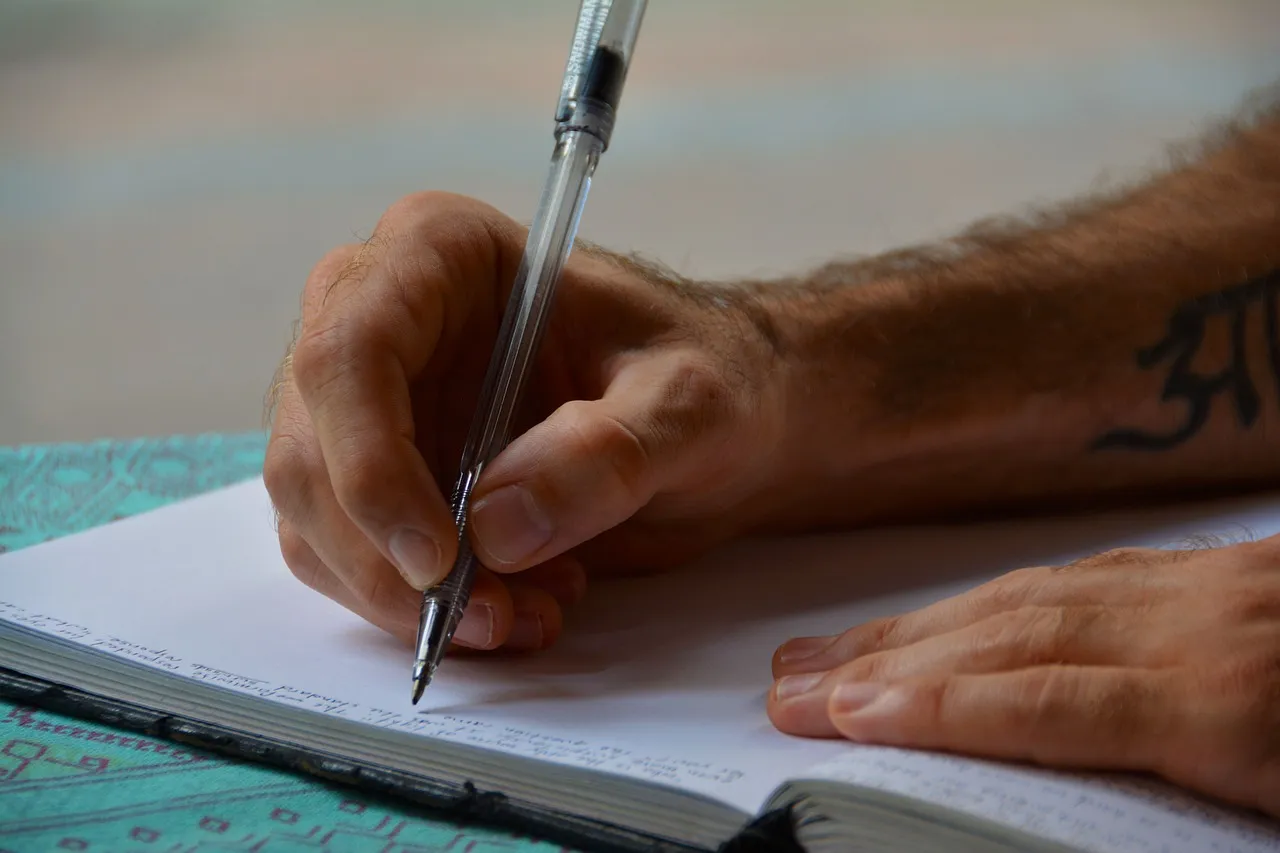個人再生とは?特徴やメリット・自己破産との違い
投稿日: 2025.02.04 | 更新日: 2025.02.14

「借金生活を解消したいけど、自己破産まではしたくない」
「財産を残したまま借金を減額したい」
そんな人におすすめなのが、個人再生です。
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理のひとつです。
基本的には、債務額を5分の1に減額し、原則3年かけて返済していく手続きのことをいいます。
大幅な借金の減額を見込める一方で、車や家などの財産を手放す必要がないため、条件を満たす場合はぜひ利用したい制度です。
この記事では、個人再生の内容やメリット、必要な期間や費用を解説します。
個人再生するべきか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。
個人再生は「債務整理」の種類のひとつです。
以下の記事で、債務整理の基本知識についてくわしく解説していますので、あわせてご確認ください。
▼関連記事
リーガルノートでは、債務整理に関するさまざまな情報を発信しています。
債務整理について相談できる、おすすめの弁護士事務所も紹介していますので、ぜひブックマークしてご覧ください。
個人再生は借金を最大で10分の1まで減らす手続き
個人再生は、借金を最大で10分の1まで減らせる手続きです。
ここでは、個人再生がどのような手続きなのか、くわしい内容や流れについて解説します。
- 民事再生法にのっとった手続き
- 裁判所に「再生計画案」を提出し、認めてもらう
- すべての借金やローンが5分の1〜10分の1まで減額される
民事再生法にのっとった手続き
個人再生は、「民事再生法」にのっとって借金を減額する手続きです。
民事再生法の第一条「目的」には、次のように書かれています。
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
【引用:民事再生法 – e-gov】
つまり、個人再生は、借金を負っている人の仕事や生活を元どおりにするために存在しているのです。
裁判所に「再生計画案」を提出し、認めてもらう
個人再生は、裁判所に「再生計画案」を提出し、認めてもらうことで手続きをします。
再生計画案とは…民事再生法にのっとって減額した借金を、今後どのように返済していくかを記載した書類。
個人再生したらどこまで借金が減るのかは、法律で定められています。
再生計画表のとおりに返済できるのか、収入や財産に偽りがないかなどを裁判所がチェックし、認可・不認可を決定する流れです。
すべての借金やローンが5分の1〜10分の1まで減額される
個人再生が認められれば、借金は5分の1〜10分の1まで減額可能です。
個人再生には「最低弁済額」が定められており、借金額に応じて、次のように返済の最低額が決められています。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
基準債権額(借金の総額)を上回る財産を所有していたり、債権者の半数以上が個人再生に反対していたりするといった事情がない限り、最低弁済額にしたがって減額される仕組みです。
減額された借金を3〜5年かけて返済する
個人再生で減額された借金は、原則3年で返済していきます。
例えば、500万円の借金が100万円まで減額された場合、36回払い(3年)で返済することになり、月々の返済額は約2.8万円です。
この場合、裁判所に「月々2.8万円の返済は無理だろう」と判断されてしまうと、手続きが却下されてしまう恐れがあります。
ただし、特別な事情があり裁判所が認めた場合は、返済期間を5年まで伸ばすことも可能です。
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法 – e-gov】
「3年でも返済できるものの、月々の返済額を減らしたいので5年払いにしたい」というケースは認められないため、注意してください。
個人再生には2種類ある
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。
それぞれの方法のメリット・デメリットは次のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 小規模個人再生 | 減額幅が大きい | 債権者の同意が必要 |
| 給与所得者再生 | 債権者の同意が不要 | 減額幅が小さい |
実際には、個人再生する人の9割以上が小規模個人再生を選択しています。
その理由や違いについて、くわしく解説します。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
- 小規模個人再生を選ぶ人が多い理由
小規模個人再生
小規模個人再生は、小規模な個人事業主(フリーランス)の利用を想定して作られた制度です。
ただし、現在ではサラリーマンやアルバイトなどの給与所得者であっても、ほとんどの人が小規模個人再生を利用しています。
小規模個人再生した場合の最低弁済額は、債務額に応じて次のように決まっています。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
例えば、借り入れ額が300万円の場合、最低弁済額は100万円です。
3年かけて返済する場合、月々の返済額は約2.8万円となります。
ただし、最低弁済額はあくまでも最低金額のため、増える可能性もあります。
また、次のいずれかに該当する場合、小規模個人再生はできない点に注意してください。
- 債権者の半数以上が反対した場合
- 反対した債権者から借り入れている借金額が、借金総額の半分以上に該当する場合
給与所得者等再生
債権者の半数以上が反対しているなど、小規模個人再生の条件に当てはまらない場合は、給与所得者等再生を選択できます。
給与所得者再生は債権者の意見を聞く必要がないものの、最低弁済額について「可処分所得」という条件が課されるのが特徴です。
可処分所得とは…現在の収入から生活に必要な支出(税金や保険料も含む)を引いたすべてのお金を、2年間返済にあてた場合の合計額を最低弁済額とするもの。
例えば、月の収入が20万円で、生活に必要な支出を引いた後に12万円残る場合、12万円 × 24ヶ月=288万円が最低弁済額になります。
3年かけて返済する場合、月々の返済額は8万円です。
被扶養者が少なく、かつ収入が多い人ほど可処分所得が大きいため、小規模個人再生に比べて最低弁済額が高くなりやすい点に注意が必要です。
小規模個人再生を選ぶ人が多い理由
令和3年の司法統計によると、個人再生する人の9割以上が小規模個人再生を選んでいます。
大きな理由は、給与所得者等再生に比べて、最低弁済額が小さくて済むことです。
また、近年では消費者金融などの金融機関が個人再生に協力することが増え、債権者の反対多数となるケースが減っていることも、理由のひとつと考えられます。
そのため、まずは小規模個人再生を検討してみて、債権者の反対が多そうなら給与所得者再生を検討するとよいでしょう。
個人再生の流れ・必要となる期間
個人再生に必要な期間は、弁護士に依頼してから返済の開始まで、半年から1年ほどが目安です。
個人再生の手続きの流れは次のとおりです。
個人再生の流れ
- 弁護士に依頼する
- 裁判所へ申立てをする
- 個人再生手続開始決定が下る
- 再生計画案を提出する
- 再生計画の認可・不認可が決定する
- 返済を開始する
再生計画の認可が下りたら、再生計画にしたがって3〜5年での完済を目指します。
個人再生の費用相場は50万〜100万円程度
個人再生にかかる費用は50万〜100万円程度で、内訳は次のとおりです。
| 弁護士費用 | 相談料・着手金・報酬金 | 30万〜60万円 |
| 裁判費用 (※各裁判所により異なる) | 収入印紙 | 1万円〜 |
| 切手代 | 数千円〜 | |
| 予納金(官報公告料) | 1万円〜 | |
| 個人再生委員の報酬 (※選任された場合) | 15万〜25万円 |
個人再生では弁護士費用と裁判費用の両方がかかるため、裁判をしない任意整理と比べると費用が膨らみやすいでしょう。
費用の比率がもっとも大きいのは弁護士への報酬金で、住宅ローン特則を利用して家を残す場合は、残さない場合に比べると費用が高くなります。
また、裁判所によっては裁判の補助役として、「個人再生委員」を選出することがあります。
その場合は、報酬として15万〜25万円の支払いが必要です。
個人再生のメリット・デメリット
ここからは、個人再生のメリットとデメリットを解説します。
良い面と悪い面の両方を把握し、個人再生するかどうかの目安にしてください。
メリット
個人再生のメリットは次のとおりです。
- 借金が大幅に減る
- 返済の催促がストップする
借金が大幅に減る
個人再生すると、最大で10分の1までと大幅に借金を減らせます。
借金を減額して毎月の支払いが減ると、生活が楽になってストレスも減ります。
精神的に前を向けるようになるため、人間関係や仕事にもいい影響を与えるかもしれません。
任意整理や特定調停の場合は利息のカット程度で、大きく借金を減らすことは難しいといえます。
そのため、「借金額が大きいものの、利息の支払いばかりで元金がなかなか減らない」という人には、個人再生が向いているでしょう。
返済の催促がストップする
個人再生すると、手続きの完了まで返済の催促がストップします。
個人再生を弁護士に依頼すると、債権者に「弁護士受任通知」が送られます。
貸金業法21条で、受任通知後の貸金業者による取り立てや督促が禁じられているため、弁護士へ依頼すると取り立てをストップできるのです。
個人再生には半年〜1年ほどかかるため、この間は返済の必要もありません。
その分を弁護士費用にあてたり、手続き完了後の支払いへ向けて積み立てたりできるため、精神的にも楽になるでしょう。
デメリット
個人再生のデメリットは次のとおりです。
- 返済ができなくなると手続きが台無しになる
- 保証人がいる場合に迷惑がかかる
- ローン中の車などは没収されるかもしれない
- 新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなる
返済ができなくなると手続きが台無しになる
個人再生の手続き後、もし返済ができなくなると、手続きそのものが取り消しになります。
お金や時間をかけて減額できた借金が取り消され、借金額が元に戻ってしまうため、延滞には注意が必要です。
ただし、3〜5年という長期間の返済の中で、経済状況が変わってしまう可能性もあるでしょう。
救済措置として、裁判所が認めた場合に限り、返済期間を2年間延長することも可能です。
取り消しになったあとでは延長手続きができないため、手遅れになる前に弁護士に相談してください。
また、条件を満たせば残りの借金が免除される「ハードシップ免責」という手続きもあります。
ハードシップ免責とは…個人再生中、本人の責任とはいえない部分で返済が困難になった場合、残りの返済を免除できる制度。
ハードシップ免責を使うためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 本人の責任ではない事情で残りの返済が困難になった
- 借金の4分の3以上をすでに返済している
- ハードシップ免責をしたことによって債権者の利益に害がない
- 再生計画を変更しても返済が困難である
どうしても返済が難しくなった場合は、早めに弁護士に相談してください。
保証人がいる場合に迷惑がかかる
個人再生すると、保証人がついている借金があった場合、借金は保証人が肩代わりすることになります。
個人再生では、すべての借金を対象に減額が行われ、対象を選ぶことはできません。
| 借り入れ先 | 保証人 | 個人再生した場合の借金 |
| Aクレジットカード | いない | 減額される |
| B消費者金融 | いない | 減額される |
| Cローン | いる | 保証人が肩代わりする |
そのため、保証人に迷惑がかかることを防ぐのは難しいでしょう。
手続きを始める前に、弁護士・本人・保証人でよく話し合うことをおすすめします。
また、借主本人は分割払いをする契約になっていても、保証人は分割払い契約になっていないことも多いです。
つまり、個人再生すると保証人が残りを一括払いしなければいけない可能性があります。
保証人がついている借金がある場合は、保証人も一緒に債務整理するか、任意整理で保証人がついている借金を除外する方法も検討してみてください。
ローン中の車などは没収されるかもしれない
個人再生した際、ローンを返済中の車などがあると、没収される可能性があります。
ローン返済中の財産は、個人再生すると借金が返済できなかったと判断され、担保としてローン会社に引き揚げられます。
家や車など、高額な財産は担保対象になってしまうのです。
車を手放したくない場合は、親や兄弟などに頼み、本人以外がローンを返済する「第三者弁済」を検討してみてください。
新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなる
個人再生に限らず、債務整理をすると、返済後5〜7年程度は新規の借り入れやクレジットカードの作成ができません。
債務整理をした情報は「信用情報機関」に記録される(いわゆる「ブラックリストに載る」)ため、ローン会社や貸金業者の審査で「返済能力がない」と判断されてしまうのです。
信用情報とは…借金に関する個人情報を記録する機関。申し込みや借り入れ額、返済状況や滞納歴などが記録されている。
借金の返済を一定期間以上滞納した場合も、同様に信用情報に記録されます。
信用情報に債務整理の事故情報が記録されている間は、プリペイドカードやデビットカードを利用する、一括払いにするなどの方法で対応してください。
個人再生するための条件
個人再生するためには、次の条件を満たしている必要があります。
個人再生するための条件
- 安定した収入がある
- 返済の意思・計画がある
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である
個人再生では手続きのあとも返済が続くため、安定した収入があり、きちんと返済していける人でなければ認められません。
また、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることも、個人再生できる条件です。
5,000万円を超えている場合は一般の民事再生の対象となり、手続きや条件がより複雑になるため注意してください。
なお、小規模個人再生する場合は、債権者の反対多数でないことも条件となります。
個人再生ができないケースとは
個人再生ができない・向かないのは、次のようなケースです。
- 継続的な安定収入が見込めない
- 債権者の反対多数だった
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以上である
- 高価な財産を所有している
- 特定の借金だけを減額したい
- 借金総額が100万円未満である
病気などの理由で働くことが難しく、継続的な安定収入が見込めない人は個人再生の対象外となるため、自己破産を検討するとよいでしょう。
債権者の反対多数だったり、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以上だったりする場合も、個人再生の対象外となります。
その他、高価な財産を所有していると最低弁済額も高くなり、減額幅が少なくなるため、個人再生には向きません。
特定の借金だけを減額したい場合や、借金総額が100万円未満の場合には、任意整理がおすすめです。
個人再生すると周りにバレる?
基本的に、個人再生して周りにバレることはありません。
裁判所や弁護士が、家族や会社に通知することはないためです。
ただし、場合によっては勤務先や家族にバレてしまうケースもあります。
周りに知られたくない人は、ここで紹介する具体例を参考にしてください。
- 勤務先にバレるケース
- 家族にバレるケース
勤務先にバレるケース
勤務先にバレるケースは、次のような場合です。
- 勤務先の会社から借り入れをしている
- 勤務先の会社が官報を見ている
- 退職金見込額証明書を発行してもらった
勤務先の会社から借り入れをしていた場合、弁護士の受任通知や裁判所の再生手続開始通知書が会社に届くため、個人再生の事実がバレる可能性があります。
また、金融関係の会社では官報をチェックしていることもあり、偶然見られることもないとはいえません。
また、手続きに必要な「退職金見込額証明書」を会社に発行してもらう際、正直な理由を伝えることでもバレてしまいます。
発行理由を「住宅ローンの審査」などとするか、退職金額を自分で計算して提出するとよいでしょう。
家族にバレるケース
家族にバレるケースは、次のような場合です。
- 債務者が主契約者の家族カードを使われた
- 家族が借金の連帯保証人だった
- 車のローンなどを返済している
個人再生するとクレジットカードが使えなくなるため、家族が家族カードを利用できなくなることでバレる恐れがあります。
また、個人再生後は連帯保証人に請求がいくため、バレる可能性は高いでしょう。
さらに、ローン返済中の車を没収されてしまい、個人再生した事実を知られることもあります。
家族にバレないためには、家族カードを使わせない、保証人にしないといった対応が必要です。
個人再生手続きを弁護士に依頼すべき理由
個人再生手続きは、弁護士に依頼するのがおすすめです。
自力でも手続きは可能ですが、裁判所へ多くの書類を提出しなければならず、作成には専門知識や経験が求められます。
また、書類に不備があったり債権者との交渉が難航したりすると、手続きが進まず時間がかかってしまう恐れもあります。
さらに、手続きの間も督促や返済が止まらないため、精神的な負担も大きくなるでしょう。
一方で、弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
弁護士に依頼すべき理由
- 自分に合った手続きができる
- 難しい手続きをすべて任せられる
- 債権者とスムーズに交渉できる
- 取り立てを止められる
- 家族などに知られないように配慮してくれる
そもそも個人再生が自分の状況に適しているかどうか、弁護士なら的確に判断可能です。
さらに、弁護士は法律のプロであると同時に、交渉のプロでもあります。
書類の作成から交渉まですべて任せられるため、スピーディーに手続きを進められるでしょう。
また、手続き中は取り立てや返済を止められることもメリットです。
さらに、書類を自宅へ送付しないようにするなど、周りに知られないよう配慮してくれることも多く、安心して手続きできます。
素人が無理をするよりも、プロに任せたほうが確実でスピーディーな手続きがかなうでしょう。
▼関連記事
債務整理におすすめの弁護士事務所ランキング8選!選び方や費用相場も解説
実際に個人再生した人の例(体験談)
ここでは、個人再生して借金を減額できた例を紹介します。
- 300万円の借金が100万円まで減額(小規模個人再生)
- 1000万円の借金が288万円まで減額(給与所得者等再生)
300万円の借金が100万円まで減額(小規模個人再生)
Aさんは300万円の借金があり、収入減などの事情で返済が困難になったため、弁護士と相談して個人再生しました。
その結果、最低弁済額まで減額でき、300万円あった借金は100万円になりました。
| 個人再生前 | 個人再生後 | |
| 借金額 | 300万円 | 100万円 |
| 金利 | 15% | 0% |
| 月々の支払い額(36回) | 約10.4万円 | 約2.8万円 |
| 支払い総額 | 約374万円 | 100万円 |
月々の支払い額が約7.6万円減り、3年で完済できる見通しもついています。
個人再生をしなければ、元々の借金額に利息も上乗せされた状態で返済しなければならなかったため、大きく状況が改善したといえるでしょう。
1000万円の借金が288万円まで減額(給与所得者等再生)
Bさんは、事業資金として1,500万円を借り入れました。
事業は順調に成長し、500万円の借金を返済したものの、コロナウイルスの影響などで売り上げが激減し廃業となってしまいます。
事業主から会社員に戻ったBさんは、個人再生で残りの1,000万円の返済をすることにしました。
Bさんの場合、1社からのみの借り入れで個人再生に関する同意が得られなかったため、債権者の同意がいらない「給与所得者等再生」で手続きしています。
| 個人再生前 | 個人再生後 | |
| 借金額 | 1,000万円 | 288万円 |
| 金利 | 5% | 0% |
| 月々の支払い額(36回) | 約30万円 | 約8万円 |
| 支払い総額 | 約1,079万円 | 288万円 |
一般的に、給与所得者等再生は最低弁済額が大きくなりやすいものの、可処分所得額(生活に必要な支出を引いたあとに残るお金)が少なければ、最低弁済額が低くなる可能性があります。
Bさんの場合、元々あった借金の3分の1以下に減額することに成功しました。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが適しているかは、状況によって異なるため、気になる場合は弁護士に相談してみてください。
個人再生に関するよくある質問
ここからは、個人再生に関するよくある質問に回答します。
- 個人再生でやってはいけないことは?
- 個人再生の成功率は?
- 個人再生における最低弁済額は?
- 個人再生の際に裁判所はどこまで調べますか?
疑問や不安な点を解消し、個人再生するかどうか検討してみてください。
個人再生でやってはいけないことは?
個人再生でやってはいけないことは次のとおりです。
- 弁護士に依頼せず自分で手続きする
- 弁護士の指示にしたがわない
- 手続き中に新たに借金をする
- 手続き後の返済をしない
弁護士に依頼せず、自分で個人再生しようと考えるのは失敗のもとです。
また、依頼後は弁護士の指示にしたがうことが必須だといえます。
もちろん、手続き中の新たな借金や、手続き後の返済をしないことも厳禁です。
個人再生の成功率は?
日本弁護士連合会の2020年の調査によると、個人再生した人の91.7%が認可決定しており、成功率は9割以上です。
個人再生が不認可となるケースには、書類に不備があったことや再生計画の成立が見込めないこと、債権者の反対にあったことなどがあります。
個人再生における最低弁済額は?
個人再生における最低弁済額は民事再生法で定められており、最低でも100万円以上です。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
例えば、借金総額が100万円の場合は、弁済額も100万円です。
借金総額が700万円の場合は「500万円超1,500万円以下」に該当するため、140万円(700万円の5分の1)が最低弁済額になります。
個人再生の際に裁判所はどこまで調べますか?
個人再生で行う主な調査は次のとおりです。
- 債務者の財産
- 債務者の借金
- 不正行為がないか
財産については、家や車などの高額な財産はもちろん、預貯金や生命保険の解約返戻金、給料などもチェックします。
通帳のコピーや給与明細など、必要な書類はすべて提出が必要です。
借金については、総額や借り入れ先、それぞれの借金がいくらあるのかを確認します。
くわえて、財産を隠していないかや、特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」をしていないかなど、厳しいチェックが入るでしょう。
財産隠しをすると、再生計画が認められなかったり、詐欺罪に問われたりするリスクがあるため、注意してください。
まとめ
- 個人再生では、借金を5分の1〜10分の1に減額できる
- 個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類がある
- 必要な費用は50万〜100万円、期間は半年〜1年が目安
- 車の没収や保証人がいる場合は注意が必要
- 個人再生は法律・交渉のプロである弁護士に任せると安心
個人再生すると、借金を5分の1〜10分の1まで減額できます。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、自分に合った方法が選べます。
個人再生に必要な費用は50万〜100万円程度で、必要な期間は半年〜1年が目安です。
減額幅が大きいことがメリットですが、ローンを払っている車が没収されたり、保証人がついている借金があると請求がいったりする点には注意が必要です。
個人再生は自分でやるよりも、法律・交渉のプロである弁護士に任せると、安心して手続きできるでしょう。
借金を減らしてストレスのない生活を手に入れるため、個人再生を検討してみてください。
リーガルノートでは、債務整理に関するさまざまな情報を発信しています。
債務整理について相談できる、おすすめの弁護士事務所も紹介していますので、ぜひブックマークしてご覧ください。
関連記事
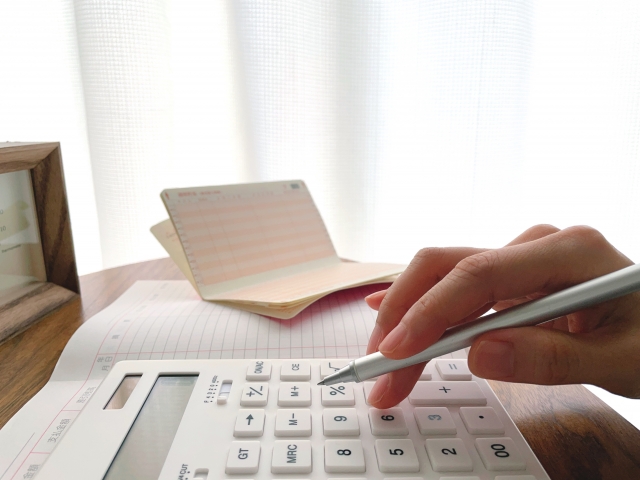
個人再生の積立金とは?返金や引き出し・期間はどうなる?
2025.08/08

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説
2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説
2025.05/27

個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説
2025.05/25

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!
2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き
2025.05/20