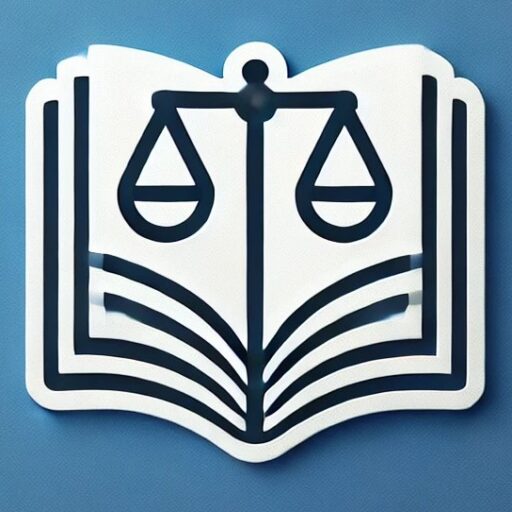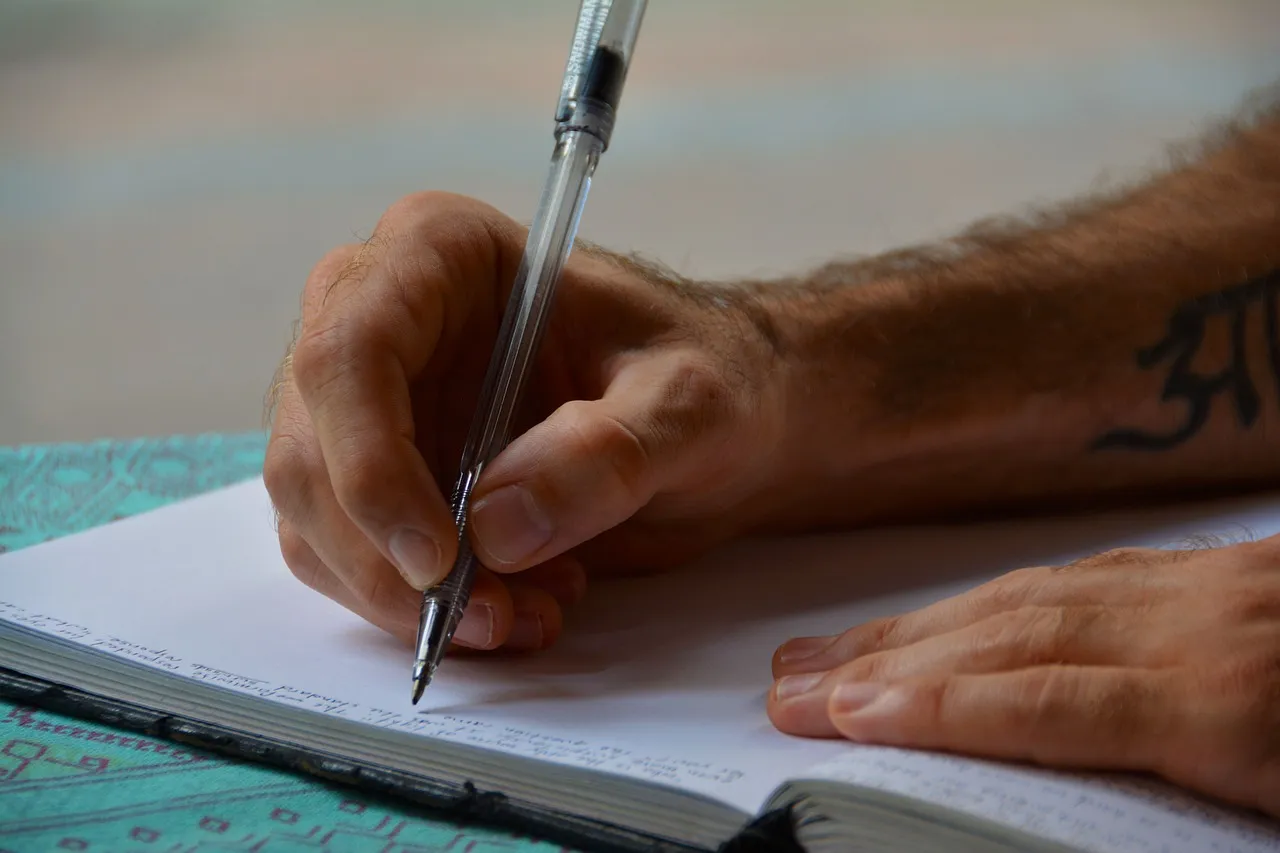個人再生の条件は?小規模個人再生と給与所得者再生の違いも解説
投稿日: 2025.05.02 | 更新日: 2025.05.02

「個人再生するための条件って?」
「個人再生でやってはいけないことや失敗事例が知りたい」
個人再生には継続的な安定収入や、借金総額が基準を満たしていることが求められます。
また、小規模個人再生と給与所得者再生のどちらを選ぶかでも条件が変わるため、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
この記事では、個人再生するための条件を解説します。
小規模個人再生と給与所得者再生の違いや、個人再生でやってはいけないこと、失敗事例なども紹介するため、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
個人再生するための基本条件

まず、個人再生するための基本条件は次の2つです。
- 継続的な収入が見込める
- 借金総額が100万円以上5,000万円以下である
それぞれチェックしてみてください。
継続的な収入が見込める
個人再生するには、将来的に継続的な収入が見込めることが条件です。
なぜなら、個人再生が認められたあとは、減額された借金を原則3年・最長5年で返済していくことになるためです。
継続的かつ安定した収入がなければ、そもそも個人再生を認めてもらうことは難しいでしょう。
借金総額が100万円以上5,000万円以下である
個人再生するには、住宅ローン以外の借金総額が100万円以上かつ5,000万円以下でなければなりません。
個人再生には、借金額に応じて次のように返済の最低額が決められています。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
個人再生する場合、最低でも100万円の支払いは発生します。
借金総額が100万円より少ない場合は個人再生の恩恵を受けにくいため、任意整理を検討するのがおすすめです。
また、借金総額が5,000万円を超える場合は民事再生手続きの対象となります。
民事再生には数百万円単位のコストがかかる上、手続きが複雑なため、住宅ローン特則の利用や過払い金請求などで5,000万円以下に抑えるといいでしょう。
小規模個人再生と給与所得者再生の条件の違い

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。
| 小規模個人再生 | 給与所得者再生 | |
| 対象者 | ・給与所得者 ・自営業者 | 給与所得者 |
| 利用条件 | ・安定収入の見込みがある ・借金総額が5,000万円以下である | ・給与などの安定した定期収入がある ・借金総額が5,000万円以下である ・過去7年以内に個人再生や自己破産をしていない |
| 減額幅 | 大きい | 小さい |
| 債権者の同意 | 必要 | 不要 |
| 弁済額 | 最低弁済額または清算価値の高いほうの額 | 最低弁済額・清算価値・可処分所得基準のうちもっとも高い額 |
この2つは、次のように利用できる条件が異なります。
- 対象者の制限
- 収入の安定性や変動幅
- 過去の債務整理履歴
- 債権者の同意
- 弁済額の基準
それぞれの違いをチェックし、どちらか自分に向いているか判断してください。
対象者の制限
小規模個人再生は給与所得者・自営業者のいずれも対象ですが、給与所得者再生の対象者は給与所得者 = サラリーマンや公務員に限られます。
そのため、自営業者やパート・アルバイトの場合は、基本的に小規模個人再生を選択することになります。
収入の安定性や変動幅
給与所得者再生は給与などの定期収入の見込みがあり、その変動幅が少ないことが条件です。
主な対象は給与所得者で、収入が不安定な個人事業主やパート・アルバイトの人の利用は難しいでしょう。
一方、小規模個人再生は会社員にくわえ、個人事業主のように定期収入がなくても、3ヶ月に1回の再生計画にもとづいた返済ができれば問題ありません。
また、アルバイトやパートであっても、雇用の継続が見込まれていれば大丈夫です。
過去の債務整理履歴
過去7年以内に個人再生や自己破産、ハードシップ免責を利用していた場合、給与所得者再生はできません。
ハードシップ免責…個人再生後に返済が難しくなったとき、条件を満たすことで残りの債務が免除されること
1回目の個人再生が小規模個人再生だった、または1回目から7年以上経っていることが、給与所得者再生を申立てられる条件です。
小規模個人再生の場合は、2回目の手続きにとくに条件はありません。
債権者の同意
個人再生の再生計画案を認可するにあたり、小規模個人再生では債権者の同意が必要になり、給与所得者再生では不要という違いもあります。
小規模個人再生では、次の条件に当てはまらないと認可が受けられません。
- 反対する債権者が全体の2分の1以下である
- 反対する債権者の債権総額が借金総額の2分の1以下である
一方、給与所得者再生では債権者の同意がいらないため、債権者の反対にあう可能性が高い場合に選択するケースもあります。
弁済額の基準
弁済額の基準は、給与所得者等再生のほうがより条件が厳しくなります。
小規模個人再生では、基本的に最低弁済額の基準に従って弁済額が決まります。
ただし、家や車などの高額な財産を保有している場合は清算価値が高くなり、最低弁済額と清算価値のいずれか高いほうが弁済額となるのです。
給与所得者等再生では、さらに「可処分所得基準」という条件が加わります。
可処分所得とは、収入から税金と最低限の生活費を差し引いた金額のことで、この2年分の返済が必要です。
可処分所得は、最低弁済額や清算価値よりも高くなるケースが多いため、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べて返済額が高くなりがちな点に注意が必要です。
個人再生の住宅ローン特則の利用条件
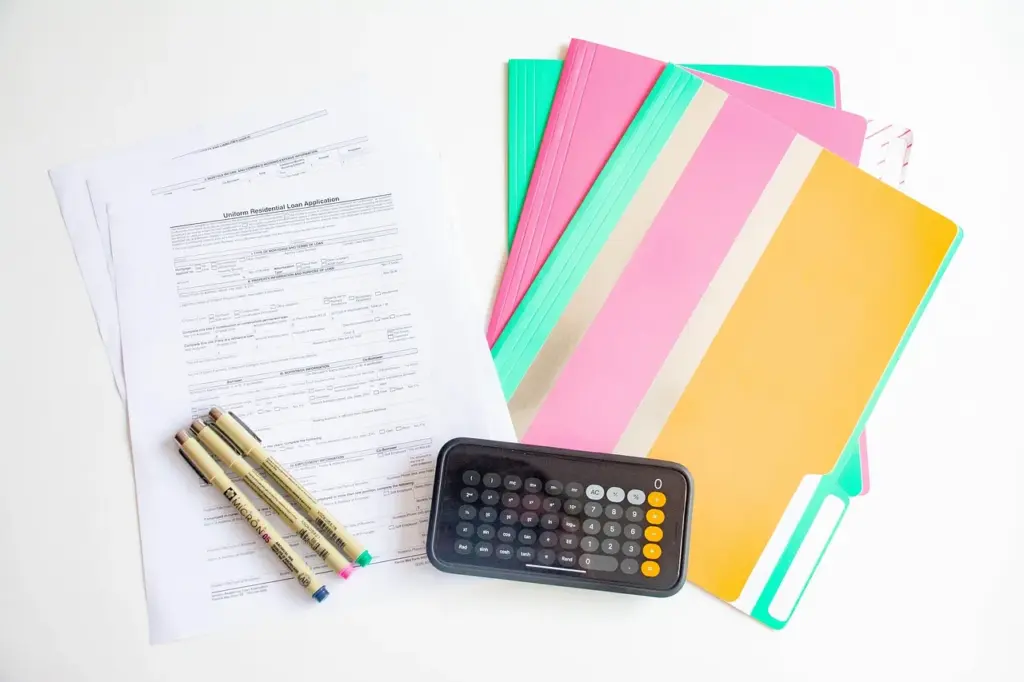
個人再生には、ローン支払い中の家を残しながら借金を整理できる「住宅ローン特則」という方法があります。
住宅ローン特則の利用条件は次のとおりです。
- 自身が所有し居住する家である
- 住宅ローン以外の抵当権がない
- 住宅ローンを滞納していない
1つずつくわしく解説します。
▼関連記事
個人再生で住宅ローン特則を利用する条件は?使えないケースも解説
自身が所有し居住する家である
住宅ローン特則は、債務者自身が所有し、居住する家に対して適用されます。
また、建物床面積の2分の1以上が居住用に利用されていることも条件です。
例えば店舗や事務所と住宅を兼ねている場合は、居住用のスペースが建物の床面積の半分以上を占めている必要があります。
住宅ローン以外の抵当権がない
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローン以外の抵当権がついていないことも条件です。
抵当権とは、支払いができなくなったときに債権者がお金に換えられる権利のことです。
例えば、住宅ローン以外のローンで抵当権が設定されていたり、すでに差し押さえられていたりする場合は、他社が抵当権を設定したとみなされ適用外となります。
住宅ローンを滞納していない
個人再生手続きを進める前に、住宅ローンの返済を滞納している場合は住宅ローン特則が利用できません。
ただし、通常は滞納から3〜6ヶ月経つと、保証会社が代わりに返済する「代位弁済」が行われます。
保証会社が代位弁済したあと、6ヶ月以内に個人再生を申立てれば、住宅ローン特則の利用は可能です。
個人再生でやってはいけないこと

個人再生の条件を満たすためには、個人再生でやってはいけないことにも注意が必要です。
- 特定の債権者へ優先して返済する
- 嘘の内容を申告する
- 新たな借入をする
- 弁護士のアドバイスを無視する
- 手続き中に仕事を辞める
- 費用を支払わない
- 履行テストを軽視する
- 手続き中に浪費する
上記のことを行うと、弁護士に辞任されたり、個人再生が不認可になったりするリスクが高まります。
くわしくは、以下の記事を参考にしてください。
▼関連記事
個人再生でやってはいけないことは?メリット・デメリットも解説
個人再生ができないケースとは?失敗する人の割合
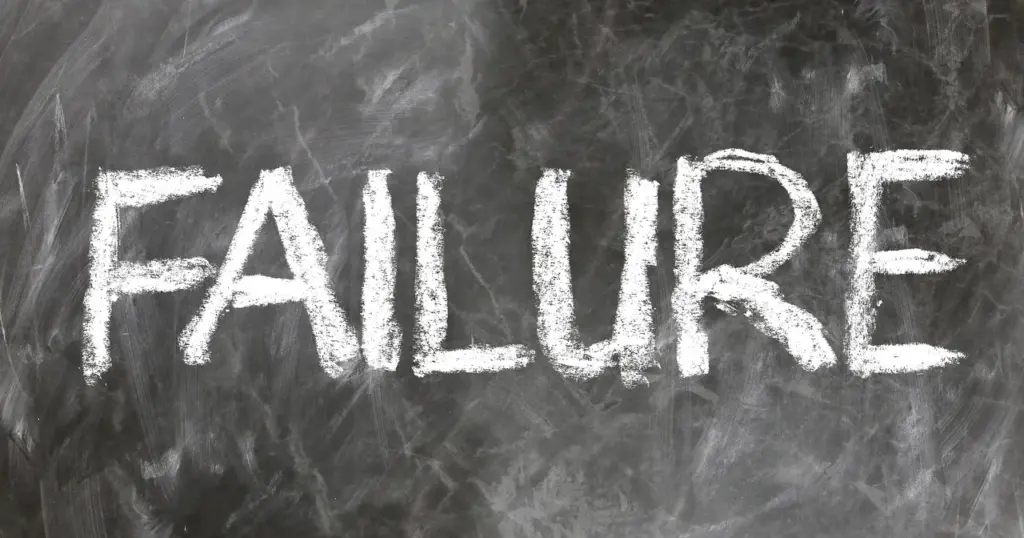
2020年の日本弁護士連合会の調査によると、個人再生の成功率は約90%と高く、不認可になる割合は1%未満でした。
| 小規模個人再生 | 給与所得者再生 | |
| 認可決定 | 92.59% | 88.24% |
| 不認可決定 | 0.34% | 0.65% |
| 失敗率 | 7.41% | 11.76% |
個人再生に失敗する理由は不認可のほか、申立却下・廃止 ・申立棄却などがあり、失敗率は約7〜11%程度です。
全体の1割程度と多くはないものの、実際に個人再生に失敗するケースもあることがわかります。
個人再生に失敗した人の体験談

ここでは、個人再生に失敗した人の体験談を紹介します。
- 債権者に反対された
- 支払い忘れで不認可になった
- 再生計画案の作成を断られた
どんなケースで失敗しやすいのかを知り、対応策の参考にしてみてください。
債権者に反対された
小規模個人再生に失敗しました。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1361736418
過半の債権者である楽天クレジットに反対され、小規模個人再生が不認可になりました。給与所得者再生では、可処分所得が年収の下がる前年も加味されるため、認可されてもその後の支払いが厳しい状態です。
小規模個人再生で過半の債権者の同意が得られず、失敗した事例です。
債権者の反対にあう可能性がある場合、給与所得者等再生が利用できますが、弁済額が高くなりやすいのがデメリットです。
こういった場合は弁護士に相談し、個人再生以外の債務整理を検討してみてもいいでしょう。
支払い忘れで不認可になった
実は過去に個人再生の認可おり、自分で支払いをするつもりでしたが、妻が家計を管理していて妻が支払いをすると言われ任せました。←これが間違いでした。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14112401224
時がすぎある日債権者から通知が来ました。裁判を起こされました。
内容は再生中に支払い忘れ不認可となりお金を支払えと
妻に聞いたら支払ったような忘れたようなの返事が
焦り裁判所に確認したらやはり支払い忘れて不認可になった事が発覚
焦り弁護士に相談したところ自己破産しかないと言われました。
その際自己破産しても個人再生失敗したら認められないかもと言われました。
個人再生中に支払いを忘れて、不認可になった事例です。
1回目が小規模個人再生だった場合や、1回目が給与所得者等再生でも7年以上経過している場合は、個人再生の2回目の申立が可能です。
また、個人再生後に返済が難しくなった場合は自己破産という選択肢もあるため、弁護士に相談してみてください。
再生計画案の作成を断られた
自宅を強制競売の申し立てをかけられてしまい個人再生を弁護士さんにお願いしてたのですが最終的に再生計画案を作れないとの事で申し立てを取り下げたいと言われました。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11100121461
弁護士に再生計画案の作成を断られた事例です。
再生計画を作成できないといわれる場合、返済能力や財産状況に問題があるかもしれません。
債務整理に強い別の弁護士に相談すると、新たな解決策が見つかる可能性もあるでしょう。
もし、家などの高額な財産があって個人再生が難しい場合は、弁護士に相談しながらの適切な財産処分や住宅ローン特則の利用も視野に入れてみてください。
▼関連記事
個人再生と任意整理・自己破産の条件の違い

ここでは、個人再生以外の債務整理手続きである、任意整理と自己破産の条件を解説します。
- 任意整理の主な条件
- 自己破産の主な条件
もし、個人再生の条件に当てはまらないようなら、任意整理や自己破産の条件もチェックしてみてください。
任意整理の主な条件
任意整理の主な条件は次のとおりです。
- 安定した継続的な収入がある
- 将来利息などをカットした残額を3~5年で返済できる見込みがある
- 債権者が交渉に応じてくれる
任意整理は、将来利息のカットや返済期間の延長を債権者に交渉する手続きです。
認められると3〜5年かけて残債を返済するため、安定収入があり、期間内に完済できる見込みがあることが条件となります。
また、裁判所をとおさず直接交渉することから、そもそも債権者が交渉に応じてくれなければなりません。
債務額が比較的少ない場合や、利息が膨らんでなかなか元金を返済できない場合に向いている方法です。
▼関連記事
任意整理とは?後悔しないために知っておきたいメリットや注意点などわかりやすく解説!
自己破産の主な条件
自己破産の主な条件は次のとおりです。
- 支払い不能状態である
- 免責不許可事由に当てはまらない
- 借金が非免責債権ではない
自己破産するには、収入や財産がない支払い不能状態であると認められなければなりません。
また、借金の理由がギャンブルだったり財産隠しを行ったりと、免責不許可事由に当てはまらないことも条件です。
さらに、借金が税金や公共料金などの非免責債権ではないことも求められます。
債務額が大きく財産もない場合や、安定収入がないなど返済が難しい場合は、自己破産が向いているでしょう。
▼関連記事
自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説
個人再生の条件に合うか迷ったら弁護士に相談を

個人再生するためには、継続的な安定収入や、借金総額が基準を満たしていることが求められます。
その上で、小規模個人再生と給与所得者再生の条件を確認し、自分に合った方法を選ぶのがおすすめです。
マイホームを残したい場合は、住宅ローン特則の利用も視野にいれるといいでしょう。
個人再生では約9割の人が成功していますが、条件を満たさずに失敗するケースもあるため、事前の確認が重要です。
弁護士に相談して条件を確認しながら、個人再生の成功を目指してください。
関連記事
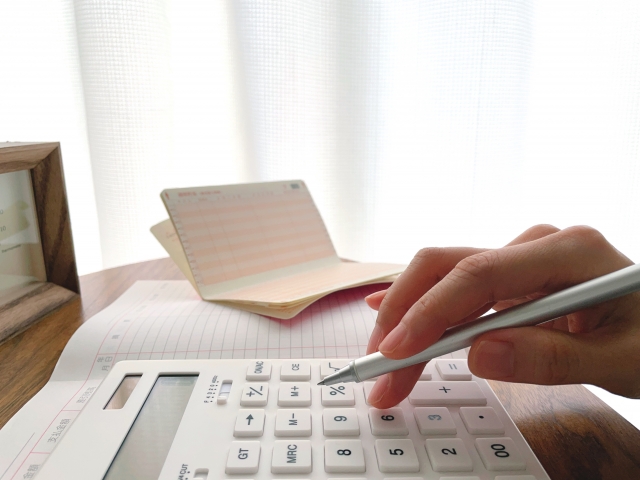
個人再生の積立金とは?返金や引き出し・期間はどうなる?
2025.08/08

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説
2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説
2025.05/27

個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説
2025.05/25

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!
2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き
2025.05/20