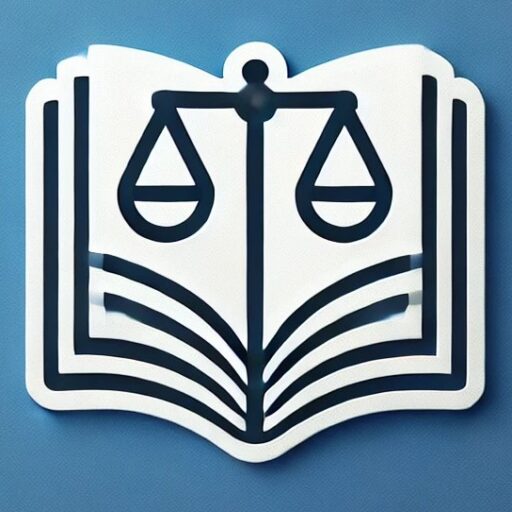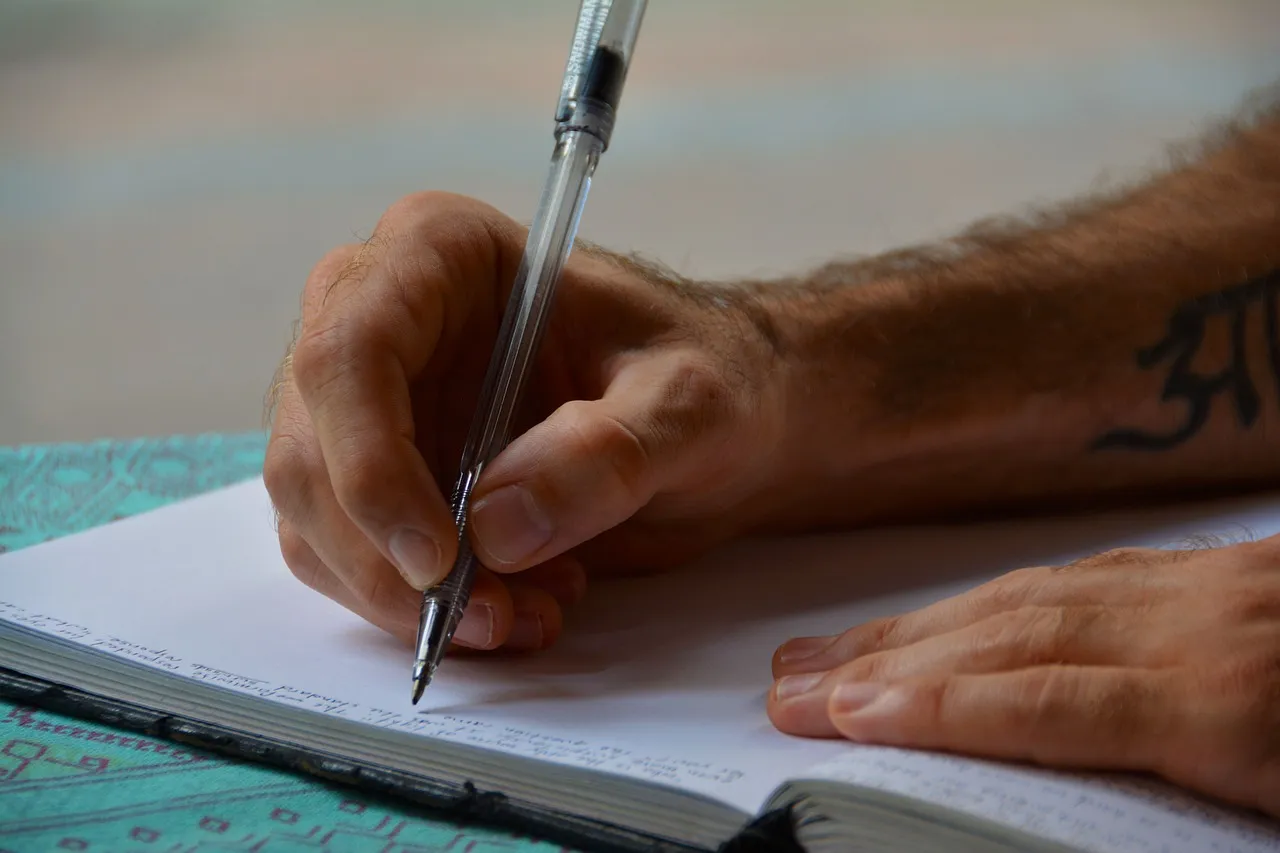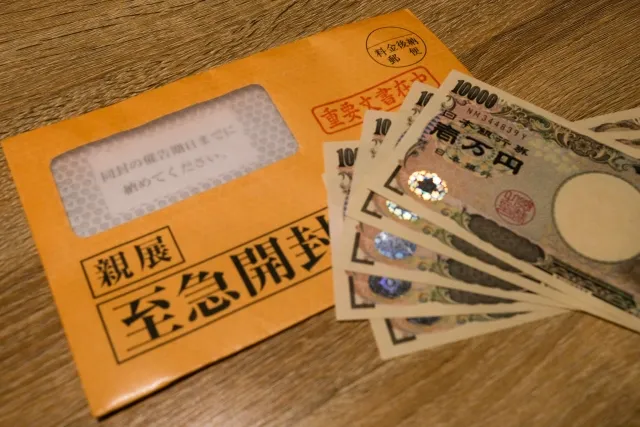個人再生のデメリットとは?家族・会社・信用情報への影響を徹底解説
投稿日: 2025.03.31 | 更新日: 2025.04.10
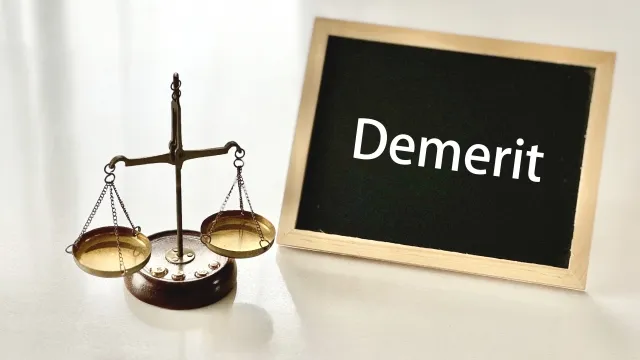
「個人再生にデメリットはある?」
「個人再生したらどんな影響があるのか知りたい」
個人再生を検討しているものの、デメリットや影響が気になって悩んでいる人もいるでしょう。
個人再生しても完全に借金がなくなるわけではなく、手続きに時間や手間もかかります。
一方で、減額幅が大きい、家や車などの財産を守れるといったメリットもあるため、総合的に判断しなければなりません。
この記事では、個人再生のデメリットや影響について解説します。個人再生のメリットや影響を受けない要素も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
債務整理のデメリットは6つ!車やクレジットは使えなくなるのか詳しく解説
個人再生のデメリット7選

個人再生のデメリットは次の7つです。
- 完全に借金がなくなるわけではない
- 高価な財産があると返済金額が増える
- 手続きに手間と時間がかかる
- 信用情報に事故情報が登録される
- 保証人に影響が及ぶ可能性がある
- 住宅ローン督促が使えない場合がある
- 官報に氏名や住所が掲載される
順番に解説します。
1.完全に借金がなくなるわけではない
個人再生しても、完全に借金がなくなるわけではありません。
自己破産のように、手続きすれば残りの借金が免除されると考えていると後悔する恐れがあるため、注意が必要です。
とはいえ、認可を受けると借金が5分の1〜最大10分の1まで大きく減額されるため、手続き前に比べると月々の返済はラクになるでしょう。
2.高価な財産があると返済金額が増える
個人再生では、家や車などの高価な財産があると、返済金額が増える可能性があります。
まず、個人再生には「最低弁済額」といって、借金額に応じた返済の最低額が定められています。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
しかし、家や車などの高価な財産があると「清算価値保障の原則」が適用され、財産を現金化した場合の金額が基準になるのです。
この場合、借金額に対する最低弁済額と、保有財産の価値のいずれか高いほうが最低弁済額として設定されます。
すると、所有している財産の総額以上を返済しなければならず、個人再生しても結果的に支払う額が増えてしまうため、慎重に検討してください。
3.手続きに手間と時間がかかる
個人再生は、手続きに手間と時間がかかることがデメリットです。
任意整理とは違って裁判所を通す手続きがあるため、弁護士に依頼後、準備期間として借金の状況の洗い出しや収支表・申立書の作成だけでも約2ヶ月かかります。
その後裁判所に申立を行い、再生計画が認可されるまでの期間は約4~6ヶ月です。
早くても半年、長ければ1年はかかり、提出する書類や借金状況のチェックもかなり細かいため、腰を据えて取り組む必要があるでしょう。
▼関連記事
4.信用情報に事故情報が登録される
個人再生すると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストの状態になります。
ブラックリストになると、借金完済後約5〜7年はクレジットカードの作成や新規の借入が難しくなります。
そのため、スマートフォンなどは一括払いで購入する、普段の支払いはバーコード決済やデビットカードを利用するなどの工夫が必要です。
ブラックリストの影響について、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
▼関連記事
債務整理のブラックリストはいつ消える?期間やリスクを徹底解説
5.保証人に影響が及ぶ可能性がある
個人再生すると、保証人や連帯保証人がいる場合は返済義務が移ります。
保証人には一括返済の義務があり、払えない場合は保証人も債務整理しなければならなくなる恐れもあります。
保証人への影響を抑えたい場合は、整理する借金を選べる任意整理を検討してみてください。
▼関連記事
任意整理とは?後悔しないために知っておきたいメリットや注意点などわかりやすく解説!
6.住宅ローン特則が使えない場合がある
個人再生では持ち家を残せることがメリットですが、場合によっては住宅ローン特則が使えないこともあります。
個人再生には、住宅ローンを支払い中の家がある場合、支払いを続けることで家を残せる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。
しかし、適用されるには次の条件を満たさなければなりません。
- 住宅ローンとして借り入れている(抵当権がついていない)
- 申立人が所有する住宅である
- 申立人が居住するための住宅である
- ほかの借入の担保になっていない
事業用として使用している住宅であるなど、上記に当てはまらない場合は対象とならないため、事前に適用条件をよく確認しておいてください。
7.官報に氏名や住所が掲載される
個人再生すると、国の広報誌である官報に氏名や住所が掲載されます。
官報には裁判所へ申立たとき、再生計画案を決議したとき、認可されたときの計3回載るため、どこかのタイミングで家族や職場の人が見る可能性はゼロではありません。
とはいえ、官報を日常的にチェックするのは金融機関関係者や法律事務所の人間など、ごく一部です。
実際には、官報から個人再生したことが周囲にバレる可能性は低いといえるでしょう。
個人再生した場合の仕事・家族・家への影響

個人再生した場合に考えられる、仕事・家族・家への影響は次のとおりです。
- 会社にバレる可能性は低く仕事への影響は少ない
- 家族への直接的な悪影響はない
- マイホームや賃貸住宅への影響は条件により異なる
それぞれ詳しく解説します。
会社にバレる可能性は低く仕事への影響は少ない
個人再生しても、会社にその事実を知られる可能性は低く、仕事への影響は少ないといえます。
また、自ら伝える必要もないため、これまでどおり問題なく仕事を続けられるでしょう。
バレるケースとしては、会社から借金をしていたり、手続きで必要な「退職金見込額証明書」を発行してもらう際にありのままの理由を伝えたりした場合です。
会社にバレたくない場合は、証明書の発行理由を「住宅ローンの審査のため」などとするといいでしょう。
家族への直接的な悪影響はない
子どもや配偶者など、同居している家族へも直接的な悪影響は及びません。
ただし、個人再生すると子どもの奨学金の保証人になれない、車を手放す場合がある、家族カードが使えなくなるなど、間接的に影響を与える可能性はあります。
家族に隠そうとしても、給与明細や通帳、法律事務所からの書類などを見られることでバレやすいため、影響がありそうな場合は手続き前に相談しておくのがおすすめです。
マイホームや賃貸住宅への影響は条件により異なる
現在住んでいる持ち家や賃貸住宅への影響は、条件によって異なります。
住宅ローン特則が適用になれば持ち家を手放す必要はなく、家族もそのまま住み続けられるため、悪影響はないでしょう。
賃貸住宅に住んでいる場合でも、個人再生したからといって追い出されるようなことはありません。
ただし、次に当てはまる場合は更新や新規契約を断られる可能性があります。
- 保証会社が審査の厳しい信販系である
- 家賃の支払い方法がクレジットカードのみである
- これまでに家賃を滞納した履歴がある
上記に当てはまる場合は、審査の緩い保証会社を選ぶ、クレジットカード以外の支払いができる物件を選ぶ、配偶者の名義で契約するなどの対処が必要です。
個人再生のメリット6選

個人再生のメリットは次の6つです。
- 借金を大幅に減額できる
- 家や車などの財産を守れる
- 借金理由による条件がない
- 職業制限が設定されない
- 長期的な返済計画を立てられる
- 督促や取り立てがストップする
個人再生にはデメリットばかりではなく、メリットも多いため、ぜひチェックしてみてください。
借金を大幅に減額できる
個人再生すると、借金額を5分の1〜最大で10分の1と大幅に減らせます。
減額幅は最低弁済額によって決まり、例えば借金が300万円なら100万円に、3000万円なら300万円になります(※小規模個人再生の場合)。
任意整理でできるのは将来利息のカットと返済期間の延長のみで、元金は減らせません。
自己破産では借金の支払い義務が免除されますが、代わりに高価な財産も失います。
借金額が比較的大きいものの、一定の財産は残したいという場合に、個人再生はぴったりだといえるでしょう。
家や車などの財産を守れる
個人再生しても、一定の条件を満たせば家や車などの財産を守れます。
車はローンを完済していること、家は住宅ローン特則が適用されることが条件です。
ただし、保有財産の価値が高い場合、最低弁済額が高くなって減額幅が小さくなる可能性があるため注意してください。
借金理由による条件がない
個人再生は、借金の理由による条件がありません。
自己破産の場合、ギャンブルや浪費で借金をした場合は認められない可能性があるのです。
借金理由によらず減額を目指したい場合は、個人再生がおすすめです。
職業制限が設定されない
個人再生しても、職業制限は設定されません。
自己破産の場合、弁護士などの士業や生命保険外交員、外交員など、他人の財産を預かる一部の職業には就けなくなります。
あくまで申立てから3〜6ヶ月程度と一時的なものですが、一旦は登録の取り消し申請が必要です。
該当する職業に就いていて影響を受けたくない場合は、個人再生が最適だといえます。
長期的な返済計画を立てられる
個人再生すると、長期的な返済計画を立てられることもメリットです。
借金は大幅に減額したうえで、3〜5年かけて無理のないペースで返済できます。
支出や家計の状況を把握した上で、プロである弁護士が返済計画を立ててくれるため、途中で支払えなくなるリスクも減らせるでしょう。
督促や取り立てがストップする
個人再生を弁護士に依頼すると、その時点で督促や取り立てがストップします。
貸金業法21条で定められているもので、弁護士の受任後は、債権者の取り立てが禁じられているのです。
個人再生の依頼から認可までは半年〜1年ほどかかり、この間は返済も必要ありません。
そのため、精神的にラクになることもメリットだといえるでしょう。
そもそも個人再生できないケースとは

注意点として、次に当てはまる場合は個人再生できない、または向いていない可能性があります。
- 収入が安定していない
- 多額の財産がある
- 借金が100万円未満である
- 借金が5,000万円を超えている
- (小規模個人再生の場合)債権者が反対している
一つずつ解説します。
収入が安定していない
収入が安定していない場合は、個人再生が認められない可能性が高いでしょう。
個人再生は借金を減額したあと、3〜5年かけて返済していく方法です。
収入が少ない、自営業で月によって収入がバラバラである、現在無職など、安定収入がない場合は「返済の見込みが立たない」と判断されてしまいます。
派遣社員など非正規雇用でも、勤続年数が長く一定の収入があれば通る可能性もあるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
多額の財産がある
多額の財産があると最低弁済額も高くなるため、減額幅が少なくなる可能性があります。
すると月々の支払い負担が大きくなり、返済が難しくなって滞納してしまうリスクがあるでしょう。
例えば2,000万円の借金があるが財産はない場合、支払いは300万円で済みます。
しかし、2,000万円の借金と1,000万円の財産がある場合、1,000万円の支払いが必要になるのです。
支払い額を減らしたいからと、財産を別の口座に移すなどの行為は「財産隠し」となり、手続きの廃止や借金の一括返済などの厳しい処罰が下るため、注意してください。
対処法としては、財産の一部を返済にあてて総額を減らすか、弁済額を増やして財産を残す方法が考えられるでしょう。
借金が100万円未満である
借金が100万円未満の場合、個人再生する意味はほぼありません。
なぜなら、最低弁済額は最低でも100万円以上に設定されており、それ以上安くなることはないためです。
借金が少額の場合は、整理する債権先を選択でき、利息のカットができる任意整理のほうが向いているでしょう。
借金が5,000万円を超えている
個人再生するには、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。
5,000万円を超えている場合は一般の民事再生の対象となり、手続きや条件が複雑になるうえ、数百万円単位の高額な費用がかかります。
そのため、5,000万円以上の借金がある場合には、自己破産を選ぶのが現実的な解決方法になるでしょう。
(小規模個人再生の場合)債権者が反対している
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類がありますが、このうち小規模個人再生では、過半数を占める債権者が同意しないと認可が下りません。
基本的に、個人再生するのは任意整理では間に合わないほど借金額が多い人です。
そんな人がもし個人再生できないと自己破産するしかなくなるため、債権者にとっては一部でも返済してもらえるよう、賛成することがほとんどです。
しかし、より多くの借金を回収したいと考えたり、会社の方針として反対したりする債権者も中には存在します。
その場合は、債権者の同意がいらない給与所得者再生での認可を目指すことになるでしょう。
個人再生のデメリットを理解し自分に合った方法を選ぼう

個人再生にはデメリットもありますが、減額幅の大きさや、条件を満たすことで家や車などの財産を残せることは大きな魅力です。
会社や家族への直接的な影響もなく、長期的な返済計画に沿って支払いを続けることで、将来の見通しも立てやすいでしょう。
ただし、安定収入がなかったり、借金が100万円未満または5,000万円を超えているといった場合は、個人再生ができないため注意が必要です。
個人再生のデメリットとメリットを理解し、何を優先するかを考えながら、自分に合った方法を選んでください。
関連記事

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説
2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説
2025.05/27

個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説
2025.05/25

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!
2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き
2025.05/20

個人再生の期間はどれくらい?手続き・返済・信用回復までの全スケジュール
2025.05/19