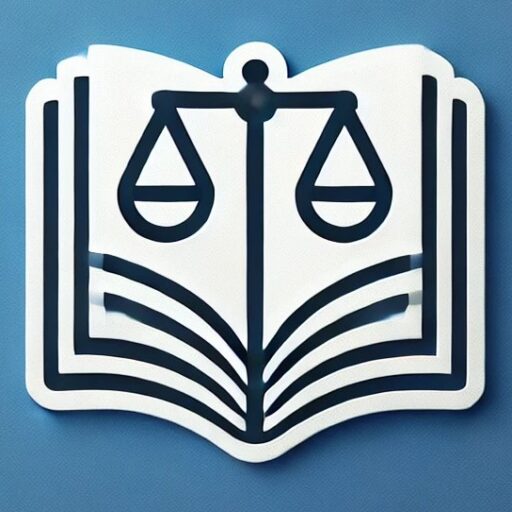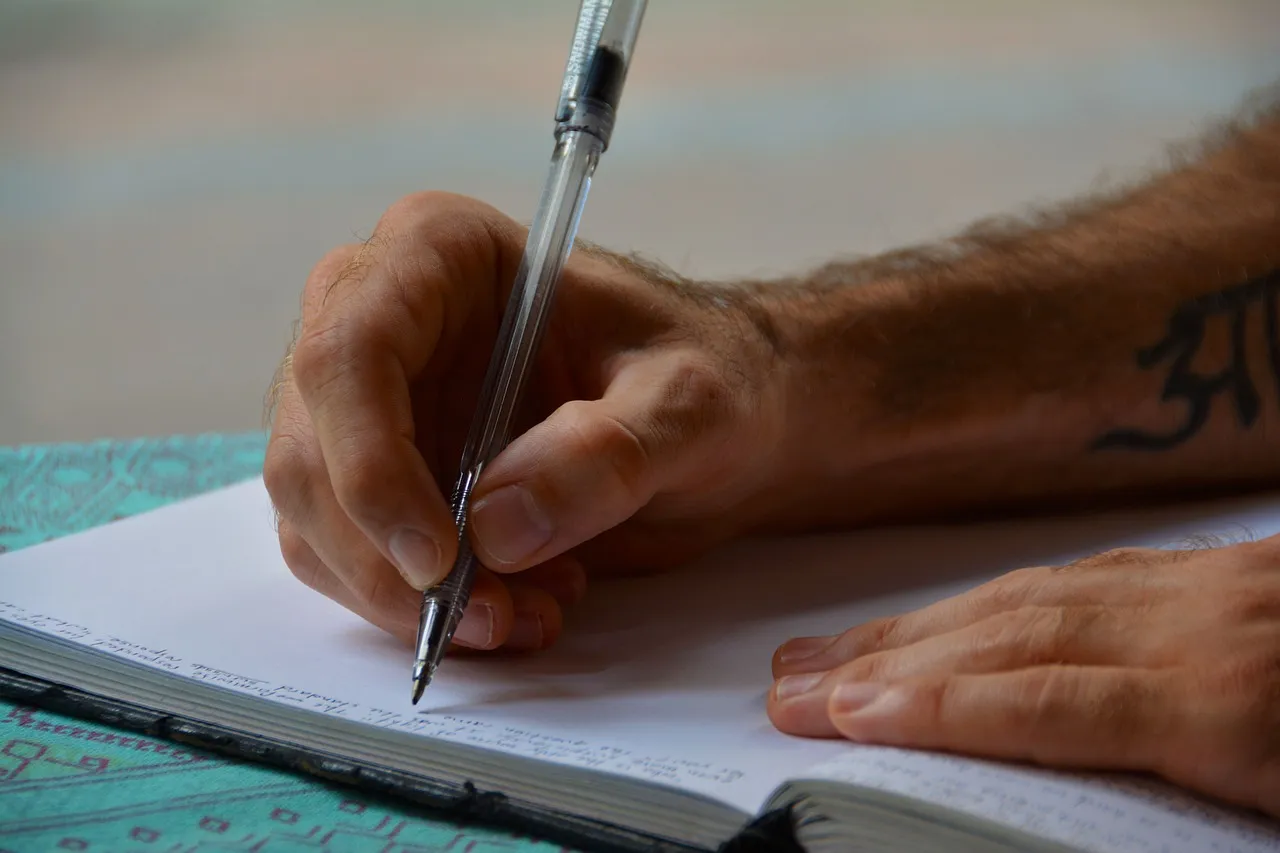個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説
投稿日: 2025.05.25 | 更新日: 2025.05.25

「個人再生の手続きってどんなことをするの?」
「個人再生手続きの流れややってはいけないことが知りたい」
個人再生は、裁判所に申立てて借金の減額を目指す債務整理手続きの1つです。
具体的にどんな手続きをするのか、条件や流れを知りたいと考える人もいるでしょう。
この記事では、種類別の個人再生手続きの条件の違いや期間・流れを解説します。
地域による違いや成功させるためのポイントも紹介するため、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
【種類別】個人再生手続きの条件の違い
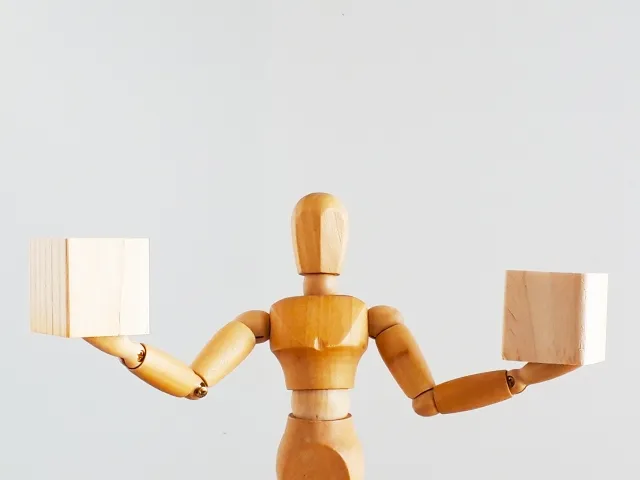
個人再生手続きには次の2種類があり、次のように条件が異なります。
| 小規模個人再生 | 給与所得者再生 | |
| 対象者 | 給与所得者自営業者 | 給与所得者 |
| 利用条件 | ・安定収入の見込みがある ・借金総額が5,000万円以下である | ・給与などの安定した定期収入がある ・借金総額が5,000万円以下である ・過去7年以内に個人再生や自己破産をしていない |
| 減額幅 | 大きい | 小さい |
| 債権者の同意 | 必要 | 不要 |
| 弁済額 | 最低弁済額または清算価値の高いほうの額 | 最低弁済額・清算価値・可処分所得基準のうちもっとも高い額 |
それぞれ詳しくチェックし、どちらが自分の状況に合っているか判断してください。
▼関連記事
個人再生の条件は?小規模個人再生と給与所得者再生の違いも解説
小規模個人再生
小規模個人再生は、安定収入の見込みがあり借金総額が5,000万円以下であることと、債権者の半数以上の同意を得られることが利用条件です。
その名のとおり、小規模な個人事業主(フリーランス)の利用を想定して作られましたが、現在ではサラリーマンやアルバイトなどの給与所得者を含め、個人再生する人のうち約9割が小規模個人再生を選択しています。
小規模個人再生の、債務額に応じた最低弁済額は次のとおりです。
| 借金額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
ただし、家や車などの高価な財産があると清算価値が高くなるため、最低弁済額と清算価値の高いほうの額が弁済額となります。
給与所得者再生
給与所得者再生は小規模個人再生よりも条件が厳しく、安定した定期収入があり借金総額が5,000万円以下であることのほか、過去7年以内に個人再生や自己破産をしていないことも条件です。
債権者の半数以上が反対しているなど、小規模個人再生の条件に当てはまらない場合は給与所得者等再生で手続きをします。
債権者の意見は不要ですが、最低弁済額・清算価値・可処分所得の2年分のうちもっとも高い金額が弁済額となります。
可処分所得とは…現在の収入から生活に必要な支出(税金や保険料も含む)を引いたすべてのお金を、2年間返済にあてた場合の合計額を最低弁済額とするもの。
被扶養者が少なく収入が多い人は可処分所得が大きくなりやすいため、小規模個人再生よりも弁済額が高くなりやすい点に注意が必要です。
個人再生の手続きにかかる期間は6ヶ月~1年程度

個人再生の手続きにかかる期間は6ヶ月~1年程度で、内訳は次のとおりです。
| 手続き | 期間 |
| 1.弁護士・司法書士への相談・依頼 | – |
| 2.申立て準備 | 1〜3ヶ月 |
| 3.裁判所への申立て | – |
| 4.再生手続開始決定 | 申立てから約20日〜1ヶ月後 |
| 5.再生計画案の提出 | 開始決定から約3ヶ月後 |
| 6.再生計画の認可決定 | 開始決定から約5ヶ月後 |
弁護士に依頼後、申立ての準備だけでも1〜3ヶ月かかり、申立てから認可決定まではさらに2〜4ヶ月を要します。
全体の流れを把握しておき、弁護士の指示に従って正しく進めれば、手続きもスムーズに運ぶでしょう。
▼関連記事
個人再生の期間はどれくらい?手続き・返済・信用回復までの全スケジュール
個人再生手続きの流れ

個人再生手続きの流れは次のとおりです。
- 専門家への相談
- 受任通知の発送
- 債権調査と引き直し計算
- 申立書類の準備
- 裁判所への申立て
- 面談もしくは書類審査の実施
- 履行テストの実施
- 再生手続きの開始決定
- 債権の届出
- 再生計画案の作成と提出
- 再生計画案に対する決議・意見聴取
- 再生計画認可決定
- 返済スタート
個人再生は手続きが複雑かつ、必要な書類も多く、もし不足があればさらに時間がかかります。
1つ1つ確認しながら、間違いのないように進めていってください。
▼関連記事
個人再生の流れ13ステップ!必要書類ややってはいけないことも解説
地域による個人再生手続きの違い
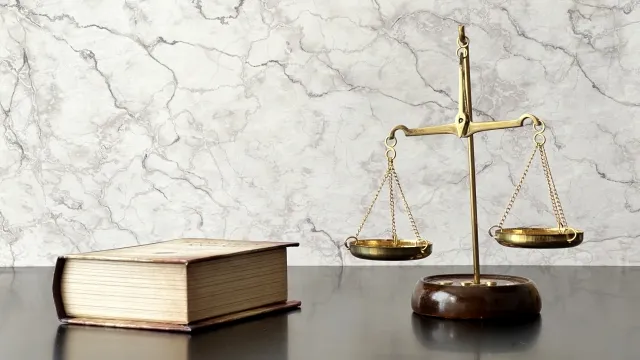
個人再生手続きには、地域による違いもあります。
- 個人再生委員の選任基準
- 個人再生委員の報酬
それぞれ確認してみてください。
個人再生委員の選任基準
まずは、個人再生委員を選任する基準の違いです。
個人再生委員とは、個人再生手続きにおいて裁判所の補助をする人で、主に弁護士が担います。
個人再生委員を選任するかは、次のように裁判所によって異なります。
| 裁判所 | 個人再生委員を選任する基準 |
| 東京地裁 前橋地裁 水戸地裁など | 全件で選任する |
| 大阪地裁 | 弁護士が申立代理人で負債総額が3,000万円以下、または負債総額が3,000万円以上でも事業による負債でない場合のみ選任しない そのほかはすべて選任する |
| 福岡地裁 | 財産や債務に問題点がある場合に選任する |
| 千葉地裁 さいたま地裁など | 弁護士を立てた場合は選任しない |
東京地裁などは全件で選任するものの、一般的には、弁護士に個人再生を依頼すると個人再生委員を選任しない裁判所のほうが多いでしょう。
個人再生委員が選任された場合、弁護士費用と裁判所費用のほかに、個人再生委員への報酬として約15〜30万円かかるため注意が必要です。
個人再生委員の報酬
個人再生手続きにおける、個人再生委員の報酬や払い方にも違いがあります。
| 裁判所 | 個人再生委員の報酬 | 支払い方法 |
| 東京地裁 | 15万円 | 分割払い |
| 千葉地裁 水戸地裁 さいたま地裁 | 20万円 | 一括払い |
| 横浜地裁 | 18万円 | 一括払い |
| 大阪地裁 | 30万円 | 一括払い |
あくまで個人再生委員が選任された場合ですが、地域によっては倍近い差が出ています。
また、分割での積み立てが認められている地域もあれば、申立て時の一括払いが原則の地域もあるため、あらかじめ居住地の裁判所の運用を確認しておくといいでしょう。
個人再生を成功させるための手続きのポイント

個人再生を成功させるための手続きのポイントは、次のとおりです。
- 経験豊富な専門家に依頼する
- 個人再生にかかる費用を把握する
- 必要書類を準備しておく
- 手続き中にやってはいけないことを理解する
順番に解説します。
経験豊富な専門家に依頼する
個人再生手続きは、経験豊富な弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
手続きが複雑で必要書類も多いため、慣れていない弁護士だと時間がかかったり、失敗したりするリスクが高まります。
まずは無料相談を利用し、実績が豊富で、親身になって話を聞いてくれる弁護士を探してみてください。
▼関連記事
個人再生にかかる費用を把握する
個人再生を成功させるためには、費用をあらかじめ把握しておくのもポイントです。
個人再生にかかる費用総額は50〜100万円程度で、内訳は次のとおりです。
| 弁護士費用 | 相談料 | 5,000円~1万円/30分 ※無料の場合もあり |
| 着手金 | 20〜40万円 | |
| 報酬金 | 住宅ローンなし:20万円〜 住宅ローンあり:30万円〜 | |
| 裁判所費用 | 官報公告料 | 1万円〜 |
| 収入印紙代 | 1万円〜 | |
| 切手代 | 数千円程度 ※債権者の数で変動 | |
| 個人再生委員の報酬 (※選任された場合) | 15〜30万円 |
弁護士費用は基本的に分割払いができますが、裁判所費用は申立て時に必ず支払わなければならないため、その分を優先して積み立てておくといいでしょう。
▼関連記事
必要書類を準備しておく
個人再生を成功させるためには、必要書類を不備なく揃えることも重要です。
書類が揃わないと申立てができず、弁護士も手続きを進められません。
個人再生手続きには財産・収入・不動産・保険など、お金にかかわるすべての書類はもちろん、通帳のコピーや、家計が同じ同居人の収入明細なども必要です。
書類を集めるだけでも数ヶ月かかる大変な作業のため、1つずつチェックしながら進めていってください。
▼関連記事
手続き中にやってはいけないことを理解する
個人再生には、次のように手続き中にやってはいけないことが存在します。
- 特定の債権者へ優先して返済する
- 嘘の内容を申告する
- 新たな借入をする
- 弁護士のアドバイスを無視する
- 手続き中に仕事を辞める
- 費用を支払わない
- 履行テストを軽視する
- 手続き中に浪費する
例えば、特定の債権者へ優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、支払った分が返済額に上乗せされたり、個人再生が認められなくなったりするリスクがあります。
虚偽申告や新たな借入れ、手続き中の浪費といった行為も、裁判所に「返済していく気がない」とみなされやすいでしょう。
また、弁護士に辞任される恐れもあるため、手続きは正しく行ってください。
▼関連記事
個人再生でやってはいけないことは?メリット・デメリットも解説
個人再生手続き中の注意点

やってはいけないことのほかにも、個人再生手続き中は次のことに注意が必要です。
- ギャンブルをしない
- 旅行は控える
- 引っ越しは裁判所に報告する
- 車を購入しない
- クレジットカードは利用できない
1つずつ解説します。
ギャンブルをしない
個人再生手続き中に、ギャンブルをすることはおすすめできません。
ギャンブルによって返済にあてるはずのお金がなくなると判断され、再生計画案が不認可になる恐れがあるでしょう。
それだけでなく、ギャンブルで消費した分の金額が返済額に上乗せされる可能性もあるため、ギャンブルは控えてください。
旅行は控える
個人再生手続き中は、旅行も避けたほうがいいでしょう。
裁判所で禁止されているわけではないものの、娯楽目的の高額な旅行は浪費と判断されかねません。
すると個人再生が認められないリスクが高まるため、手続きが終わるまでは、浪費と思われる行為は謹んでください。
引っ越しは裁判所に報告する
個人再生の申立て後に引っ越す場合は、裁判所に報告しなければなりません。
手続きをスムーズに進めるため、常に住所を明らかにし連絡がつく状態であることが求められるのです。
引っ越し自体に制限はないため、報告さえすれば手続き中に行っても大丈夫です。
ただし、引っ越しによって管轄の裁判所が変わる場合には、あらかじめ弁護士に相談してください。
車を購入しない
個人再生手続き中は、車の購入も控えるべきだといえます。
高額な財産があると清算価値が増え、それだけ最低弁済額も上がってしまうためです。
手続きが終わるまでは、車以外の代替手段で乗り切るようにしてください。
クレジットカードは利用できない
個人再生すると、保有しているクレジットカードは強制解約され利用できなくなります。
信用情報に事故情報が登録されるため、新規発行も難しいでしょう。
事故情報は借金の完済から5〜7年経つまで消えないことから、クレジットカード以外の支払い方法を活用してみてください。
▼関連記事
個人再生するとクレジットカードはどうなる?いつ作れる?代替手段も紹介
個人再生と他の債務整理手続きの違いとは?

ここでは、個人再生と他の債務整理手続きの違いを解説します。
- 任意整理との違い:借金を選べるかどうか
- 自己破産との違い:残せる財産や減額できる金額
より自分に合った方法がないか、チェックしてみてください。
任意整理との違い:借金を選べるかどうか
任意整理と個人再生の手続きの違いは、借金を選べるかどうかです。
任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息をカットするもので、整理する借金を選べるのが特徴です。
例えば保証人に迷惑をかけたくない場合は、個人再生ではなく任意整理にし、対象の借金を外すこともできます。
個人再生に比べると減額幅は小さいものの、特定の借金だけを整理したい場合に向いている方法です。
▼関連記事
任意整理とは?後悔しないために知っておきたいメリットや注意点などわかりやすく解説!
自己破産との違い:残せる財産や減額できる金額
自己破産と個人再生の手続きは、残せる財産や減額できる金額に違いがあります。
自己破産では財産を残せないかわりに、残りの借金の支払いが免除されます。
個人再生では、借金の減額はできても3〜5年間は返済が続くため、自己破産のほうが生活を立て直しやすいといえるでしょう。
ただし、持ち家に関しては、個人再生の住宅ローン特則を利用すると残せる可能性があります。
残したい高価な財産があるかや、手続き完了後に返済を続けていけるかで、自己破産と個人再生のどちらを選ぶか判断するといいでしょう。
▼関連記事
自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説
個人再生で住宅ローン特則を利用する条件は?使えないケースも解説
個人再生手続きに迷ったら弁護士に相談しよう

個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
それぞれの条件をチェックし、自分に合った手続きを選んでください。
また、個人再生の全体の流れや期間・費用・必要書類、地域による違いを把握しておくことも大切です。
手続き中のギャンブルや旅行は控え、経験豊富な弁護士に相談しながら確実に進めていってください。
関連記事
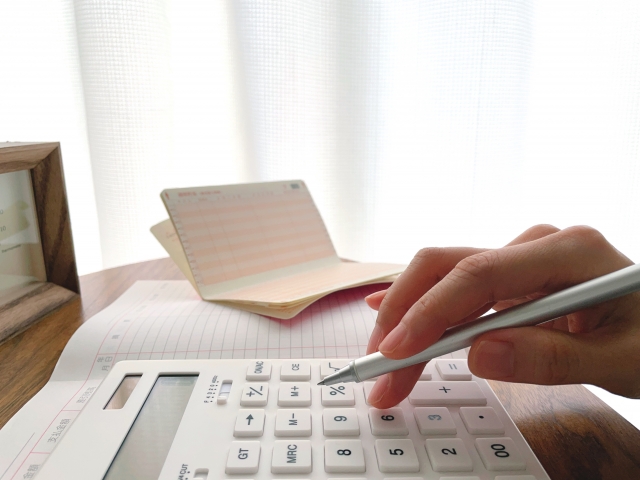
個人再生の積立金とは?返金や引き出し・期間はどうなる?
2025.08/08

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説
2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説
2025.05/27

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!
2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き
2025.05/20

個人再生の期間はどれくらい?手続き・返済・信用回復までの全スケジュール
2025.05/19